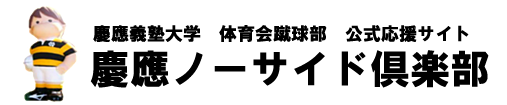悲運のスローフォワード
(1985年1月6日 大学選手権決勝 同志社大学戦)
(世田谷の塾員 編)
慶應義塾大学體育会蹴球部を語る上で、誰もが忘れられない試合の一つが、1985年1月6日の大学選手権決勝 同志社大学戦だろう。
このシーズン、松永敏弘主将に率いられた蹴球部は、対抗戦、慶明戦、早慶戦を、奇跡の逆転で勝利し、当時の大学ラグビー界の王者、同志社大学に、大学選手権決勝で挑んだ。
今でこそ、フィジカル・アドバンテージを活かした帝京大学の9連覇という記録があるが、それ以外の歴史では、大学選手権を3連覇したチームはない。
この年の同志社は、この3連覇に挑むチャンピオン・チームであり、平尾、大八木、木村、東田という、4人の日本代表を擁する、正に無敵集団であった。
巷間の評価は、どちらが勝つかではなく、同志社が何点差で勝つか、そして、おそらく日本選手権決勝で当たるであろう、新日鉄釜石に勝利できるか、に注目が集まっていた。
当時の闘いが如何に感動的なものであったか。それは、小生の個人的な感想ではなく、当時の記録・報道を紐解き、現代に蘇らせよう。以下は、
『激突!最強軍団 同志社フィフティーン(1985→1986)(岡村啓嗣著 旺文社)』
より引用させていただいた。
「嵐の前の静けさ」
(同志社大学ラグビー部)岡部長、渋谷コーチとは別に電車を乗り継いで国立競技場入りした同志社フィフティーンは、スタンドを埋め尽くした大観衆に少し驚かされていた。
「ワアー、よう入っているなあ、今日は・・・」
国立競技場の観客席は超満員だったのだ。この時、目の前では、新日鉄釜石と神戸製鋼の間で、社会人選手権の決勝が行われていた。前半三十四分で新日鉄釜石が10対0でリード。点差こそ開いていたが、神戸製鋼の頑張りで白熱した好ゲームになっていた。しかし、それにしては、観客席の湧き方は、意外なほどおとなしかった。
「なんや、よう入っているわりには静かなもんやな」
大八木が屈託ない表情でつぶやいた。彼らは、まだ知らなかった。この静けさが、“嵐の前の静けさ”だったということを。
同志社フィフティーンは、前半の終わりまで見届けると、
「よし、15日(日本選手権の相手)は、釜石だ」
と、口元をほころばせ安心したような表情でロッカールームに消えていった。フィフティーンには、15日を闘うのは自分達だ、という自負があったのだ。
国立競技場正面スタンド真下の練習用トラックでは、両フィフティーンによる軽い練習が始まっていた。慶應フォワード第一列のスクラム練習を見て、ケガで出場できない中村剛がポツリと言った。
「あいつら、うまくなったなあ」
4か月前に行われた同志社と慶應の定期戦では、木村、上滝、中村の同志社フロントローが慶應フォワードを後半スクラムで圧倒して、31対7で大勝していた。中村は、慶應フロントローが、その時に比べて、わずか3か月余りの間に格段の進歩をしたことに驚いていたのだ。
「やはり対抗戦でもまれてくると違うな」
というのが正直な感想だった。しかし、その中村でさえ、同志社のスクラムが慶應フォワードの押しの前に崩壊寸前までゆくとは、この時点では思ってもいなかったのである。
試合前のフィフティーンには早稲田戦の時と違って余裕すら感じられた。
「心配なのはスクラムだけです。でも相手が慶應だったら、勝つ自信はあります。毎年慶應とは必ず、一、二回はやっているし、負ける相手ではありません。」
フォワード・リーダーの土田の言葉がフィフティーンの気持ちを代弁していた。
「キックオフ」
キックオフを前にして、グラウンドでは各社のカメラマン達が、今か今かと両チームの入場を待ち構えていた。カメラマンの間では、どちらが先に出てくるかを言い当てるのが一つの楽しみになっている。
「どっちだと思う?」
「慶應が先だろう。」
「どうして?」
「何故なら、はやる気持ちを抑えきれなく、出てきちゃうのさ。」
「同志社は、以前、あまり早く出過ぎて気持ちを集中できず失敗したことがあるんですよ。」
とは、大学選手権1回戦、対帝京大戦の前に、同志社の堺哲也主務が話していた言葉だ。
果たして、先にグラウンドに出てきたのは・・・。
1時55分。平尾誠二を先頭に同志社フィフティーンが入場してきた。バックスタンドの同志社応援席から紫の小旗が振られる。慶應フィフティーンはそれより遅れること3分。1時58分に入ってきた。ほとんどの選手が泣きながら走ってくる。グラウンドに出ても、芝生の上にゴロンと打愛の字に寝て、空を見ている橋本達也(1番・PR)。正座して、ジーっと一点を見つめている中野忠幸(3番・PR)。慶應フィフティーンには、なにか恐ろしいような気迫がみなぎっていた。
午後2時。主審の斎藤直樹レフリーの右手が高々と上がった。前半40分は同志社が風下でゲームをする。そして注目のファースト・スクラムは、キックオフの3分後、慶應陣内10メートルに入ったところで組まれた。慶應ボールである。同志社フォワードは皆が懸念
した通り、このファースト・スクラムから慶應に押された。しかし同志社フォワードは、早い球出しで、バックスにボールを回し、むしろ慶應陣内でゲームを進めることの方が多かった。前半5分。右ラインアウトからのボールを平尾が取ると、慶應ディフェンスを、まるでスキーの回転競技のような鋭角なステップで次々とかわし、右隅にトライ。赤山のコンバートも決まり、6対0で同志社リード。
続いて前半17分、今度は同志社陣内から松尾がハイパントを上げ。フォワードラッシュで森川―浦野―馬場―武藤とつなぎ、最後、児玉耕樹(9番・SH)がボールを取ってトライ。慶應の得意技であるキック・アンド・ラッシュ戦法をまるでお手本でも見せるように同志社が決めてしまった。
同志社 10-0 慶應
「あ、これは(慶應も)たいしたことないわ」
と、松尾勝博(10番・SO)は思った。事実、前半、20分間の慶應のディフェンスと言ったら、同志社のそれとは全く力が違うように感じられた。
「30点は開けられるな」(土田)
「力の差がありすぎるから、スクラム押されても関係ないみたいだ」(浦野)
「もう、すっかり勝った気になった」(清水剛志、11番・WTB)
と、同志社フィフティーンに楽勝ムードが漂い始めるのも無理はなかった。国立競技場を埋めた6万の慶應ファンもシュンとしてしまって、バックスタンドの一角で応援を続ける同志社ファンの声だけが元気一杯だった。
しかし、前半27分過ぎから慶應の猛反撃が始まった。28分にPGを浅田が慎重に決めると(同志社10-3慶應)、慶應に本来の動きが戻ってきた。
開き直った慶應は、フォワードで勝負するために伝統のキック・アンド・ラッシュ戦法をとってきた。とにかく慶應がボールを持つと、SO浅田武夫がハイパントを上げる。そして、ボールの落ちてくる地点にフォワードがラッシュをかけてくる。この浅田のハイパントが、同志社の痛いところに、グサッ、グサッと刺さるように決まった。同志社は、この空中戦に、巨漢ロックの大八木を前面に出して対抗したが、慶應フォワードの突込みのスピードは想像以上に激しかった。ボールを取った大八木めがけて四人、五人の慶應フォワードが凄まじいタックルをかけてくる。そしてスクラムになると、グーッと押して同志社フォワードを崩しにかかる。慶應ボールのスクラムになれば、そこからまたSO浅田にボールを回してハイパントを上げる。それを目掛けて慶應フォワード第三列の量FLが突進だ、同志社フォワードは戻れないから、同志社バックスが慶應フォワードと空中戦をやることになる。慶應フォワードの早いタックルに赤山や松尾がふっ飛ぶ。じりっ、じりっと同志社ディフェンスは後退していった。
渋谷コーチが心配したとおり、スクラムの崩れから試合の流れは、完全に慶應のものになってしまった。
ここで斎藤レフェリーの笛が鳴り、前半が終わった。
同志社10-3慶應
ハーフタイムは、準決勝・対早稲田戦のような余裕はなく、皆ピリピリしていた。最初にトライを二つもとって、楽勝気分になっていただけに、慶應に勢いがついて押され出すと、
「おかしい、こんなはずでは」と弱気になってしまうのだ。
気持ちを整える間もなく、後半開始のホイッスルが鳴った。慶應ボールのキックオフだ。
慶應のキック・アンド・ラッシュがまた始まった。スクラムで同志社を圧倒し始めた慶應にとって、これに優る戦法はなかった。ハイパントを上げてフォワードを前に突っ込ましさえすればよいのだ。空中戦で相手にボールを取られても、素早いタックルで相手を倒しすればスクラムを得られる可能性が大だ。たとえ同志社ボールのスクラムでも一押しすれば、同志社スクラムはめくりあがる。スクラムさえ圧倒すれば、そんな強いチームにだって勝てるのだ。
後半に入ると、同志社スクラムは崩壊寸前になった。同志社ボールのスクラムになっても、SH児玉がスクラムにボールを入れた瞬間に慶應スクラムの押しにあって崩されてしまっている。同志社フォワードは、この劣勢をなんとか速い球出しをしてバックスにつないで、松尾、平尾のタッチキックでかろうじてしのいでいた。
スクラムは八人対八人の勝負のようだが、実は前一列の一対一の勝負といえる。だから押されると相手にコンプレックスを持つ。相手は益々調子に乗ってくる・・・。
もうそうなるとどうしようもないのだ。木村敏武だけは、
「スクラム押されているけど、俺は負けていない」
と、自分に言い聞かせた。事実、スクラムでは木村のところだけは負けていなかった。
後半5分過ぎ、押しに押していた慶應がペナルティキックを得て、浅田が慎重にこれを決めた。
同志社10-6慶應
と、ワンチャンスで逆転、というところまで同志社は追い詰められたのである。
「地鳴り」
満員の国立競技場は、異様などよめきに包まれていた。6万の大観衆のうち9割が慶應ファンもしくは慶應ひいきという中で、慶應にボールが渡ると、「ワア!」という大歓声が湧きおこった。
それは、まるで大きな「地鳴り」のようであった。
最前線で慶應フォワードとぶつかりっているフォワードの選手にとってはそれほどでもないが、後ろで待機するバックスのその大歓声は次第に大きなプレッシャーとなってゆく。
「大歓声のたび、体が浮き上がるようだった」(SO・松尾勝博)
「実際に押されている以上に劣勢に立っているような気持に段々なっていった」(FB・綾城高志)
「慶應がボールを持った時にタックルに行くのは僕らですね。慶應の攻めとともに、あの大歓声があがると何万人にも責められているような気になって、タックルにいっても、止まらないんじゃないかと・・・」(WTB・赤山泰規)
同志社フォワードは、慶應フォワードの押しの前に崩壊寸前であった。後半も10分を過ぎると、同志社ボールのスクラムでさえ、押されて慶應にボールを取られてしまう有様だった。
ゲームリーダーの平尾が大声で言う。
「一秒だけでいい。スクラムをがっちり耐えてくれ。そしたら速い球出しでバックスが展開して勝負できるから・・・。」
ところが、
「マイボールをスクラムに入れた瞬間に、ぐっと押され崩されてしまった」(No8・土田雅人)。
それは、ただの押され方ではなかった。同志社フォワードの誰もが経験したことのないような“徹底した押し”だった。慶應は、ロスタイムも入れて90分近いゲームの中で、すべてのスクラムを全力で押してきた。その体力と気力は信じがたいものであった。
SH・児玉耕樹は、自分の目の前でフォワードが壊滅してゆくのがしんじられないことのように思えた。児玉は、気の強さではチームでも一、二を争うという。その気の強い児玉が。いらだち、怒鳴り、フォワードの背をたたき。こめかみをピクピクとひきつらせていた。俊敏なフライング・パスがモットーの児玉には全くの悪夢としかいいようがなかった。
この同志社のピンチを何とか救っていたのが同志社バックスのラインディフェンスだった。特に平尾誠二、福井俊之の両センター、そしてFB・綾城高志のタックルで慶應のアタックをことごとく止めていた。しかし、それももう限界だった。
「スクラムが安定していないと、どんな優秀なバックスも動揺します。まして、あんなに押されてしまったら・・・」(渋谷コーチ)。
同志社ボールのスクラムからやっと出たボールを平尾がノックオンする・・・。
信じられないようなプレーが同志社バックスに出始めていた。WTB・清水剛志のディフェンス・ポイントも少しずつ狂いだしていた。
「同志社の力はまだあると思うのですが、慶應がそれを出させていない、という展開ですね、終盤に強い慶應のことですから、これはひょっとしたら、ひょっとするかもしれません。」(NHK解説者席に座った日比野弘早稲田ラグビー部監督)
そして後半27分、慶應は絶好のチャンスをつかむのである。
SH・児玉耕樹のオフサイドの反則から、慶應SO浅田武男が、その地点からまたもハイパントを上げてフォワードを走らせる。そのボールを大八木がキャッチするが、慶應フォワードの信じられないような早いタックルでつぶされ、児玉がこぼれ球をかろうじてタッチダウン。同志社ゴール左隅で慶應に5メートルスクラムが与えられた。慶應が狙うのは、もちろんスクラムトライだ。観客席は総立ちとなり、「ケイオー」の大コールが始まる。
そんな雰囲気の中、プレーは再開された。慶應SH・生田久貴がスクラムにボールを入れる。慶應フォワードが押す、押す。同志社フォワードが崩れてレフェリーが笛を鳴らす。観客席の慶應コールが、地鳴りのような「ウオーン」という大きなどよめきに変わる。
スクラムアゲイン。再びSH・生田がボールを入れる。同志社ゴールまであと3メートル、慶應が押す、慶應が押す、同志社フォワードはじりじりと下がり続ける。土田の足がゴールラインにかかる・・・。たまらず右ウイングの赤山までがスクラムを支えに入る・・・。ボールがでた!慶應フォワードが殺到する。トライか!しかしレフェリーの笛は慶應のノック・オン。今度は同志社ボールのスクラムに変わった。
「ここだ、ここだぞ」
平尾が手をたたいて、ここが頑張りどころだ、とフォワードを励ます。しかし、同志社ボールのスクラムは、ボールを入れた瞬間に、慶應の押しの前にいとも簡単に崩されてしまった。かろうじてタッチダウン。またも慶應に5メートルスクラムが与えられた。
スタンドの慶應ファンは総立ちだ。今度こそスクラム・トライだ!再び慶應コールの嵐だ。
慶應のスクラムが押す、同志社のフォワードがじりじり下がる。同志社のスクラムが崩れて、またしてもスクラム・アゲイン。あとゴールラインまで4メートルもない!
「もう、あかん」
FLの浦野健介は観念した。このまま何度もスクラムを崩せば認定トライをとられるのは目に見えている。主審の斎藤レフェリーは、認定トライを割と早く採る人だ。昨年10月の明治との定期戦では、同じような場面で4回のスクラムで明治に認定トライを与えたと、浦野は記憶していた。
「とられたら、あかんぞ。ここが踏ん張りどころやぞ」
LOの圓井良の声が悲愴感を帯びて聞こえてくる。
スクラムの後ろでラインディフェンスをしく同志社バックスは、たまらない気持ちになっていた。絶体絶命の大ピンチなのだ。CTB福井俊之は、ちらっと平尾の方を見やった。慶應ボールでスクラムを組んでいるのに、なんと平尾はスクラムに背を向けて後ろ向きに立っている。
「ああ・・・。平尾さん、とうとう気が狂いよった。早くディフェンスしなきゃならんのに・・・、こっち、こっち」福井の顔が引きつった。
平尾はもちろん気が狂った訳ではない。彼は後ろを向いて、電光掲示板の時計を見ながら、ある考えを頭の中にめぐらしていたのだった。時計は29分を指していた。
「ロスタイムを入れて残り15分か。よし、ここは慶應にスクラム・トライをさせてしまえ。この位置だったら今日の浅田の調子だったら、コンバート・キックはまず入らないだろう。そしたら10-10の同点で同志社ボールのキックオフだ。同点になったら、うちの選手の気合の入り方もまた違ってくる筈だ。そうしたら、残り15分で必ずもう一度突き放せる。点を取られるなら今だ。しかし下手にスクラムで頑張っていたら認定トライを採られるだろう。そうなっては、コンバート・キックはゴール正面だから10-12と逆転されてしまう。そうなる前にスクラム・トライさせてしまおう・・・」
平尾はこう決断したのだ。再度スクラム・アゲインになった時、フォワード・リーダーの土田に言った。
「いいか、スクラムトライさせてしまえ。その代わり、スクラムを崩して外へさせるんだ」
ポストからより遠いところにトライさせれば、浅田のコンバート・キックが入る確率は低くなる。土田には、平尾の考え方がすぐ理解できた。偶然だが、土田も全く同じ考えを持っていたのだ。前半25分過ぎから今に至るまですべての試合の流れが慶應の方を向いていた。同志社の流れなどひとつもなかったのである。この流れを変えるためには、むしろ慶應にトライをさせてしまった方がいいのではないか・・・と。慶應の猛攻の前に追い詰められ、平尾も土田もとうとう開き直ったのであった。
再びスクラムが組まれた。同志社ゴールまで3メートルである。ボールが入れられた。慶應が押す、押す。同志社が下がる、下がる・・。あと1メートル50・・。その時、信じられないことに慶應スクラムの中からボールがポロリと同志社側にこぼれ落ちた。正面でそれを拾ったSO・松尾があわててキックでタッチに蹴りだした。
「ウワーン」という金属音のような大きなどよめきが、国立競技場の空に渦巻いた。とりあえず同志社は大きなピンチを脱したのだ。しかし、平尾は、
「内心、切り抜けて“ほっ”とした反面、トライされていたらよかったのにと思いました。変に我慢して35分頃取られた10-12になったらいやだったし、まずそうなったら慶應陣内に攻め込むのは無理だと思いましたから・・・。実際、あのゲームは最後の10分間の駆け引きがとても難しかった」と語るのだった。
ここまで競り合ったゲームになってくると、選手の中には自分のプレーをするのに必死で信じられないような錯覚をする者も出てくる。LOの圓井良は語る。
「この時まで、僕はスコアを勘違いしていて、10-3の7点差のリードだとおもっていたのです。この試合は残り10分で7点差のリードでも危ない、と思っていたら、ふとスコアボードを見たら、10-6でしょ。4点差だったら、ワンチャンスで逆転です。それを知った時、全身が恐怖のあまり、こわばったのを覚えています。」
「逆転か!」
同志社と慶應の闘いは、最後の10分間に入っていた。この年の慶應は、対抗戦でも残り10分というところで、対明治戦を8-7、対早稲田戦を12-11とすべて逆転で勝ってきている。同志社フィフティーンも十分それを意識していた。ましてや10点前後のスコアは慶應が最も得意とする試合パターンであった。
ゲームリーダーの平尾誠二は、このまま慶應がハイパントを上げ、キック・アンド・ラッシュで攻めてきたら、
「逆転されるのは時間の問題」
と、読んでいた。なぜならハイパントを上げて一対一の空中戦に持ち込めばボール目掛けてどちらが取るか、気力と気力の勝負となる。気力の勝負だったら、この試合では慶應が断然まさっていた。それにフォワードで圧倒的優位に立っている慶應にどうしても分が出てくる。しかし、慶應がバックスにボールを回してくるのだったら、これはアタックとディフェンスの技術対技術の勝負になる。これだったら同志社バックスが負けるはずがない・・、と。
平尾は、最後の10分間を慶應ボールになるたびに大声で怒鳴った。
「ハイパントで来るぞ。ディフェンスラインを下げろ。下がれ!」
同志社のディフェンスラインが下がり、ハイパント攻撃に備えているのを見て取ると、慶應バックスは逆にハイパントを上げずに、ボールを外へ外へと回して展開してきた。慶應は押し込みながらもなかなか点を取れないフォワード勝負を諦め、バックス勝負に切り替えてきたのであった。
「しめた、助かった!」
平尾と福井を要とする同志社のラインディフェンスが、ことごとく慶應バックスのアタックをつぶしていった。
逆に32分には、平尾が独特の速いステップで慶應ディフェンスラインを突き破り、並走してきた土田にパス、土田が、50メートル6秒3の快速で右タッチライン沿いを慶應陣内になだれ込み、最後、チーム一の俊足 赤山泰規にきれいなパスを決めた。赤山の前には慶應の選手は誰もいない。赤山がゴール目掛けて快速を飛ばしている・・・。
「決まった!トライが決まった!これで慶應を突き放せるぞ、やった・・・」
同志社フィフティーンの誰もが、赤山の劇的なトライを信じて疑わなかった。しかし、次の瞬間、信じられないことが起こる。逆サイドにいた慶應の14番・若林俊康がものすごいスピードで赤山を追走、ゴールの2メートル手前で追いつき赤山をつかんで倒してしまったのだ。追走してきた児玉、森川が「ウワーッ」と思わず両手で顔を覆って天を仰ぐ。慶應のちょっとした虚をつき決定的なチャンスを作った同志社だったが、慶應の執念に食い止められた。
陽はすでに西に傾き、日没前の夕陽に選手たちの体を赤く照らされていた。時は刻一刻とノーサイドに向けて刻まれていった。両フィフティーンにとって、この一年間の、いや今までのすべてがこの最後の数分間に賭けられていた。それほど試合内容は苛酷なものになっていた。
電光掲示板の時計が38分を指した。慶應に最後のチャンスが訪れていた。久しぶりに慶應に浅田からのハイパント攻撃が出て同志社がタッチダウンで逃げ、同志社ゴールライン右隅で5メートルスクラムが慶應に与えられた。慶應は再びスクラムトライを狙ってくる。このピンチに同志社フォワードは、前一列を組み換えて対応した。疲れ切ってPRの馬場新をHOに、そしてHOの森川進豪がPRの一に入った。2年生の森川進豪のアイデアだった。スクラムが組まれた。慶應SH・生田がボールを入れる。その瞬間、同志社フォワードがプッシュをかける。森川の気迫が、対面の慶應を押し込む。スクラムトライを狙うはずの慶應フォワードが逆に押され、崩れ始めた。慶應ハーフ団は、素早くボールを出し、バックスに回して展開した。しかし慶應には、これがかえって幸いした。同志社バックスのディフェンス陣は、まさか慶應が5メートルスクラムからスクラムトライを狙わずにバックスにボールを回してくるとは夢にも思っていなかったのである。まして自軍フォワードが前一列を組み換えて対抗しているとは、ほとんどの選手が気付いていなかった。
ラインディフェンスの要といわれるCTB・福井俊之もその落とし穴に完全にはまっていた。慶應バックスは、SH・生田から浅田へ、そして浅田から一人飛ばして主将・松永俊宏へパス。松永がボールを持って。福井の内側に切り込んできた。飛び出しすぎていた福井のサイドを松永がタックルをかわして抜いてゆく。
「アアーッ」
と、誰かが叫んだ。本来ならカバーの入らなくてはならないはずの平尾まで、慶應バックスの林の動きにつられて入っていない。松永の目には、誰もいないゴールラインが映った。
「勝った!」
慶應フィフティーンは確信した。しかしその時、FL浦野健介の目が松永の下半身をとらえた。浦野は危険を感じて走りに走っていたのだ。本来なら、直前までスクラムを組んでいたフォワードの選手のタックルが届く位置ではない。
「タックルだ、つぶせ」
浦野はもはや闘争本能だけで動いていた。松永の膝のあたりに肩から思いっきり入った。
「ガクッ」
と松永の体が崩れる音がした。手応えは十分だった。
「ギリギリ間に合った。つぶせた!」
浦野は当然ダウンボールになったと思った。
しかし、松永は後ろから来たFB・村井にパス、村井はボールを受け取ると、真っ直ぐにゴールラインに走ってゆく。松永にタックルをかわされ、グラウンドに膝をついた福井は四つん這いになって、
「やめてくれ!」
と、思いっきり叫んでいた。
浦野はゆっくりと顔を上げた。するとスローモーションビデオを見るかのように、慶應FB・村井大次郎のダイビングトライが目に入ってきた。
スタンドの大歓声。思わず時計を見る・・・39分、「負けた」・・・、浦野はグラウンドに顔を伏せた。
浦野のすぐ脇を走っていたNO.8の土田雅人は、自分の目の前で村井のガッツポーズを見た。トライはゴールの真下である。逆転だ。
「終わった・・・。」体の力が抜けていった。
1月15日の日本選手権では、自分たちが新日鉄釜石と雌雄を決すると思っていた同志社フィフティーンは茫然とその場に立ち尽くした。
(以上、『激突!最強軍団 同志社フィフティーン(1985→1986)(岡村啓嗣著 旺文社)』より引用)
この最後の松永主将からFB・村井大次郎へのラスト・パスが、斎藤直樹レフェリーに「スローフォワード」と判定され、後世まで、
「幻のトライ」あるいは「悲運のスローフォワード」
として、語り継がれている。
この試合は、結局、10-12で、慶應は敗れた。しかし、この試合は多くの人々に深い感銘を与えた。翌日の報道から引用したい。
(『サンケイスポーツ』(1985年1月7日)より引用)
『観戦記 森重隆(新日鉄釜石前監督<当時>、現日本ラグビー協会会長)』
「すばらしい試合だった。『俺たちは前座でよかったよ(社会人決勝の試合が同日第一試合)』と、釜石の連中がいっていたほど、同志社大―慶大戦には感動した。99%劣勢といわれながら、残り1%にかけた慶大の気迫。きざな言い方だが、慶大に『男』を感じた。全国の指導者は、『ラグビーはハートだ、魂だ』ということを再確認したと思う。」
以上