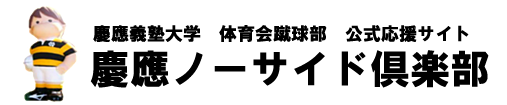逆転の慶應、対抗戦全勝優勝!
(1984年11月23日 対抗戦 早慶戦)
(世田谷の塾員 編)
この年、蹴球部は対抗戦を全勝で走り抜け、最終戦となる早慶戦を、国立競技場で迎えた。
特にこの試合に先立つ慶明戦は、ノーサイド直前、インジュアリー・タイムに入ってから、フォワード、バックス一体になって、つなぎにつないで最後のワン・プレーで逆転トライを決めた見事な試合であった。当時の記録に基づいて掲載する。以下、
『ノーサイド伝説 ―激闘!早慶明ラグビー― 馬場信浩著 講談社1985年、「魂の慶應ラグビー」』より引用(試合経過中心)
その日、観衆は、何が起きるかを知っていた。これから始まるものはなにか。それはまごうことのない本物の勝負であった。
続々とファンは集まってきた。青山門から、千駄ヶ谷門から、国立競技場へ人々の流れは切ることがなかった。
四谷署は6万2千人と観客数を発表した。しかし、それは正確な数字ではない。おそらくは7万人を超えていたと思われる。試合開始に先立つ1時間前には、すでに一般席は売り切れていた。そして場内はぎっしりと観客で埋まっていた。
「ほんとうによく入った。それは初めての経験でしたから、鳥肌が立つようでした。」そういうのは石井勝尉(早稲田、FB)である。
石井はその日、誰よりも早く目が覚めていた。自分は早稲田伝統の大型FBとして注目されている。FBはラインの最後の砦として、守備に攻撃に参加する。その任務は重い。先輩の話では、早稲田には名人といわれたフルバックが何人もいた。名前だけで、プレーは知らないが、萬谷勝利。植山信幸、といった先輩のプレーは神話として残っている。では自分はどうなのだ、と、石井は自問する。すると小さな不安がふっと湧いて、そして消える。自分はあれだけの練習をこなしてきたのではないか。自分は誰にも負けないだけの体ができているはずだ。そう思う。そして今日はこの右足に存分働いてもらわねばならない。そう思うと、そっと膝を撫でてみるのだった。
(試合前)、控室に入った市瀬豊和(慶應、WTB)は、ゆっくりとストッキングをはいていた。みんなは淡々としているように見えた。しかし、自分は少なからず不安であった。今まで、ずっとフルバックをやってきたのに、今日初めてウィングをやらされるのだ。が、じたばたしても始まらない。こんな時こそ、監督の言う、自分に勝たなければならないのだ。市瀬はそう思うと、すっくと立ちあがった。
「一つ一つ大事に戦ってきましたから、この試合に勝てばどうのこうのという感慨はありませんでした。でも、いろんなことが、特に山中湖のきつかった日々が思い出されてきたりしました」と今、市瀬は言う。
時間がきた。控室に雄叫びがこだました。
「さあ、いくぞ」
両軍はグラウンドに飛び出した。
真下レフェリーが両キャプテンを呼び寄せた。トスの結果、慶應がアタックをとった。早稲田は右サイドを守る。快晴のグラウンドに、SO浅田の影がくっきり浮かび上がった。
レフェリーの笛が鳴った。浅田は、ポン、と左足を振り上げた。それが浅田の癖であった。助走に入った。キックされたボールは、早稲田フォワードの頭上を越えた。FB石井がキャッチした。
石井勝尉はこの日、体の芯から湧いてくるような不思議な力に、驚いていた。ラグビー選手はどんなに気力が充実していても、爪一枚剥がす怪我で、最悪の事態になりかねない。幸い、今シーズンはたいした怪我もなく、無事にここまでやってきた。今日は守りに徹するのではなく、攻めてみたい。ライン参加のチャンスがあれば、どんどん仕掛けてみたいのだ。そう石井は思っていた。
石井のキックは大きな弧を描いて慶應陣に飛んだ。この石井のキックに、観客性から拍手が起こった。滞空時間の長い、正確なキックはそれだけで美しかった。
浅田武男のキックはやや短い。だが、このキックはフォワードを走らせるのに有効なものだ。石井のキックが、敵陣に放つ豪快な大砲だとするなら、浅田のキックは擲弾筒だった。それは鋭く効果的に敵陣に突き刺さる。
浅田のキックに合わせて走りこんだ慶應のFL陣。そのスピードに早稲田首脳陣から感嘆の声が上がる。速い。素晴らしい出足だ。それに姿勢が低い。あれに当たられたら、いかに鍛えてあるといっても、早稲田フォワードは無傷ではすまない。そう思えたのである。
「慶應のフォワードの特長は、当たって痛いことです。」
そういうのは明大の選手たちである。大きく強いフォワードを自認する明大選手ですら、敬意を込めて慶應フォワードをそう評する。
ここ数分の当たりあいで負けたら、それこそ80分間、負け犬になってしまう。両軍ともその事を十分承知している。肉のぶつかる鈍い音が響く。
2分過ぎ、慶應ボールのスクラムとなった今シーズン、早慶が初めて組むスクラムである。
俗に、ファーストスクラムは、その勝負の明暗を占うのによく使われる。だが、戦っている選手たちには、いかほどのこともないのだという。しかし、果たしてそうだろうか。やはり組んだ瞬間、相手の強さ、重さ、気力などがのしかかってきて、ファイトが湧くのではないか。注目のファーストスクラム、という言葉には、勝手にファンがつけたものではない。観客が息を詰めてその瞬間を見守る。
組んだ。両軍の一列の首の取り合いにはいった。低い姿勢で相手を押し返そうとする。しかし、スクラムは崩れた。
「意地、フォワードにはありますよね。負けられんですよ。慶應さんには」
そういうのは尾形勉である。尾形の突込みは定評があった。石巻高出身の尾形は寡黙である。春のオープン戦対明大戦を見ながら、童顔に笑いを浮かべ、言葉少なに表現してくれた。
石巻高から育ったラガーメンは多い。だが同じ東北の秋田工、黒沢尻工に押されて、今一つ、伸び悩んでいるというのが実情だろう。石巻高OBの熱い眼差しが注がれている。尾形勉は唇を噛み締めながら、その声援にうなずく。
2分半、再度組み直されたスクラム。慶應が低くプッシュをかけた。早稲田は右オープンに展開する。球は早稲田に出た。SHからSOの森田博志に渡った。森田は背中に石井勝尉の意気を感じていた。
「奴は上がってくる」
森田がそう直感する。と、迷わず石井が上がってきているであろう地点にパスを放った。
若林俊康は、自分の対面である鈴木学の動きを、目をさらにして見張っていた。鈴木学が走り出した。倒さなければならない。誰であっても、一発で倒さなければならない。そう思っていた。だが、いつの間にか、鈴木から石井に標的が変わっていた。しかし、それはどうでもいいことであった。171センチの若林は、181センチの石井にあたった。
これが二人の運命的対決の序奏となった。
石井勝尉の胴体を半分するようなタックルが決まった。
「ラグビーはタックルですよね。これでのりこえた。そんな感じはしました。僕なんか、ラグビーやりたくて慶應に行ったでしょう。慶應は花園組なんかいませんしね。ここならおもいっきり走れる。そう思っていました」
若林俊康は言った。
「あいつのタックルがきた時、下からうまくはいりやがったなという感じでした。春には引き分けていましたし、慶應は何をするかわからんチームではないでしょう。正攻法でくる筈ですから、若林俊康のタックルだって、こんなものだろうくらいにしか、思っていませんでした。」
そう石井は言う。
このタックルは早稲田のラインの進撃を止める効果があった。飛び出していたバックスは戻り切れない。真下レフェリーの手が上がっていた。アドバンテージをみている。この展開では、慶應有利とならないと判断したレフェリーは、早稲田のオフサイドを宣していた。
PGを狙うには絶好の位置であった。
「こんなに早くPGのチャンスがくるとは思っていませんでした。このチャンスは若林俊康のタックルがもたらしたものです。その意気に応えてやらなければなりません」
浅田武男はそう言う。
3分、浅田のキックは軽く、楽々とゴールを割った。3対0、慶應がまず先制した。
「僕、あのキックを見ていて、震えがおきていたんです。くそったれ、そう浅田にやすやすと決められてたまるか。きっと取り戻してやる。そう思っていました」
そう言って森田は唇をきっと結ぶ。
森田は現在、試合状況、の判断力、走力、キック力、そして敏捷性ということでは大学ラグビー界屈指のSOである。その時、森田は自分の判断を見透かしたようにとびかかってきた相手WTB若林俊康とSO浅田武男に、怒りに似た闘志を、燃え立たせていたのである。
早稲田ボールのスクラムとなった、ガッと音がするような組み方であった。ボールの入る前に押すのは違法だが、はやる闘志は自制心も吹き飛ばしてしまう。慶應が押した。たまらず早稲田一列がつぶれた。
尾形は顔色を変えていた。なめられてたまるか。一列同士の戦いで負けるわけにはいかなかった。それがたとえボールインの前であってもである。
キックの応酬があって、早稲田が慶應22メートル付近まで攻め込む。
「ここで一発、サインプレーをやってみようと思ったのです。松尾さんからボールを貰うと僕が直接スクラムのサイドを突くというものでした。これは日体大戦でも使ったものでした。」と森田は言う。
「ここでなんかしかけてくる。そんな気がしました。それがなんであるかはわかりませんが、マークをしっかりしていれば抜かれることはよもやないと思っていました。ですから彼らが突っ込んできた時は、ただ普段の練習通り、タックルに入っただけでした」
そういうのは玉塚である。
森田はたまらずノックオン。だが、予測していたとはいえ、この攻撃は守る慶應に嫌な気分を与えた。
今度は慶應ボールのスクラムである。早稲田の一列は意地でも良いポジションをとらす訳にはいかなかった。また首の取り合いが始まった、スクラムが崩れ、ラック状になった。苦しい球出しながら慶應に出た。浅田はチャージに来る両センターの間隙をぬってキックを上げた。
このキックはよく伸びた。そしてタッチに切れた。
「うちの浅田にしても、早稲田の森田にしても、小柄です。小柄なSOというのは素早く動いて、敵の穴をつく。それができるかどうか、また、それを阻止できるかどうかという点に、SOの勝負はかかってくるんです。」
というのは慶應の堀越である。浅田、森田の対決はさらにエスカレートしていく。
早稲田ボールのラインアウトになった。投げ入れるのは米倉である。スローイングがびしっと決まった。松尾が素早く森田にパスすると、森田は全軍投入の態勢を敷いた。
吉川が、土肥が、石井が駆け上がった。
「きたっ。そんな感じだったな。最後の決め手は石井勝尉だろうとは思っていました。もし、その読みが外れたら・・・。」
そういうのは村井である。石井へのタックルはまともに入った。石井は横倒しになった。
石井は倒れながら、ボールの行方を目で追った。
春とは違う。慶應の当たりが、全く違う。言葉では言い表せないが、タックルを受けてみてその違いがわかる。負けてたまるか、そう思うと石井は、芝をひきちぎるように立ち上がる。
球がこぼれてタッチの外へ出た。バックスタンドで、
「さあ、早稲田とって帰ろう」の声援が起きる。
「守れ、守るんだ」は慶應の声援だ。慶應のゴールまであと5メートルほどしかない。歓声がひときわ大きくなった。
19分、米倉が何ごとか叫ぶ。投げ入れ前のサインだろうか。投げた。ラインアウトに並ぶ選手の列が崩れ、たちまち混戦状態になった。どっちが球を支配しているのか分からない。米倉が突く。ディフェンスに玉塚が、田代が戻る。そこへ最も強く、鋭い出足で飛び込んだ奴がいた。
「球がある、というのは匂いのようなものです。そこへただ無心で飛び込みました」
主将矢ケ部博の突入だった。
「矢ケ部は名主将ですよ。彼がいてくれれば、なんでもビシリと決まるし、だからと言って無理強いすることはないし、信頼なんて言葉は、彼のためにあるんじゃないですかね」
そういうのは山田浩史である。
矢ケ部は、球を拾い上げると、後ろから走りこんでくるであろう早稲田の選手に、それを手渡した。矢ケ部博はその選手の背番号を見た。9番だった。9番松尾は、低い姿勢で慶應のゴールへ飛び込んでいった。
耳をつんざくような歓声が上がった。真下レフェリーの手が上がった。トライだった。私はこのトライを、ほぼ真横から見た。それは、まさに早稲田のゴール際の執念を、見せつけるようなトライであった。立ち上がった松尾は、矢ケ部にポンと肩を叩かれていた。これで、3対4。早稲田は逆転していた。
「本来、僕の役目はいいタイミングでバックスに球を供給してやることです。でも、あの時、パスするより自分で飛び込む方が、早いと判断したのです。」
バックスタンドよりハーフライン上での早稲田ボールのスクラムであった。
松尾は微かなサインを土肥におくる。ブラインドつまりバックスタンド側を攻めるというものであった。松尾はボールインと同時に右側に走った。スクラムから出た球をとると、そのまま展開した。自ら球をとって走れるだけ走るつもりであった。
「このコース、僕の最も好きなコースです。後ろを走ってくる土肥の息遣いが聞こえてきそうです。そこで放しました」
土肥はかける。ワンバウンドした球が、浮いてくれれば、胸にすっぽりはいってトライだ。土肥はそう思うと己の体をトップスピードにのせた。が、球はわずかに左にそれた、ノックオンだった。
「あれが胸に入っていたら、行けたと思います。ディフェンスは一人だったでしょう。残念だなあ」と土肥は言った。
もみあいの後、早稲田ボールのラインアウトになった。
米倉が投げ入れると同時に異変が起きた。ラインアウト巧者と言われている早稲田フォワード陣がもたついたのだ。その瞬間を。慶應NO8の良塚は見逃さなかった。浮いた球を叩き落すようにして奪った。そして。スルッと抜け出てきた。二歩、三歩と突き進む。早稲田のウィングが必至のディフェンスに肉迫。当たった。が、これを振り切れない。ここまでと思った良塚は、生田に後をたくした。
「このパターン、どれほど待っていたか。早稲田のバックスのほとんどが戻り切れず、戦線が混乱しています。僕がとって浅田さんにパスすれば、きっとハイパントです。勢いのついた慶應フォワードはそのまま敵陣になだれこめます」
そういうのはSHの生田である。
生田の言う通り、浅田はきっちりとしたハイパントを上げた。
「足よ、砕けろって感じで上げました。早稲田のFB石井が上がっていましたからね。そこを狙って、蹴ったわけです」
浅田の狙い通り、蹴られたボールは、慶應フォワードの足で追いつく、ぎりぎりの滞空時間を稼いでくれた。
「あの展開になるとは予想していませんでした。うちは大体ラインアウトに強かったですからね。少し上がって守る、それが当たり前でした。ところがNO8に深くえぐられた。もう必死で戻りましたよ」と石井は言う。
石井は戻り切れなかった。そのためうまくキャッチできなかった。だが、必死で戻り早稲田フォワードの頑張りでなんとか持ちこたえることに成功した。
「この渡り合いの中で、僕が額を切るのですが、行ける、そんな実感がどんどん湧いてきて、気が立ってくるというのでしょう。もう武者震いの連続でした。」
橋本はそういう。
橋本は白いバンデージで額をきりきりと巻き上げた。橋本への声援が熱く飛ぶ。橋本がグラウンドに入る前、いつも一歩立ち止まって、頭を下げる。その真摯な態度を知る者は多い。慶應の顔といっていい橋本の額から、赤く糸をひくような血が流れた。
「あの体をみてやって下さい。鍛えに鍛えた慶應のフォワードの身体です。どんなかこくなトレーニングメニューでも弱音を吐かずについてきたやつらです」
そういうのは小野寺孝(慶應ラグビー部コーチ)である。
小野寺は、ここ8年のコーチ生活をふりかえっていた。柴田、和崎、田川、中崎、そして上田のもとで一貫して、フィットネス(体づくり)を担当してきた。
80分をフルに戦う体力づくり。それが小野寺に課せられた任務であった。小野寺はその範をアメリカンフットボールに見出していた。パワーとパワーのぶつかるアメリカンフットボールは、ラグビーと共通点が多い。アメリカでは、そのトレーニング法が確立されている。小野寺は指導書を読み、実際のコーチに会って、自分の考えが正しいことを確信していく。また仕事の合間をぬって、オーストラリアのシドニーに出かけ、コーチ技術習得の講習を、受けたりしていた。
そして確立されたものは、学生たちにとって苛酷という言葉が当てはまる、凄まじいトレーニング法であった。
小野寺は学生にそれを要求するだけではなく、自らもロ-ドワークに出て、その苦しさを体験していく。世に、口ばかりのコーチが多い中、この小野寺の指導方法は、学生達の心の中にしみ込んでいった。
「もちろん、私一人の勝手な考えで、自由にやったわけではありません。強化委員長の堀越の意見も入れ、歴代監督の意向も取り入れながらやってきたわけです」
小野寺は慶應のコーチ陣のチームワークの良さにも言及した。そして。
「フィットネスとはすこし違うかもしれませんが、タックルポイントに入ったら、姿勢を低くして飛び込まなければなりませんね。これはなかなか厄介なんです。この練習方法にハードルを潜ってタックルに、というのを開発したんです。またこれだけでは足りませんのでボールを置いて、走りながら尻をボールにつけていく。そうすることによって自然と姿勢が低くなる。そんな工夫もしていたんです」とも言う。
ラグビーの練習には各大学が独自に開発したものが数多くある、中でも、このハードルくぐりは見事なアイデアだと感心させられる。費用も場所も取らず、選手も興味を持つに違いない方法であった。
25分、その時うねるような歓声が巻き起こった。ラインアウトの攻防を繰り返していた戦況が、一転してオープンへの攻撃となった。
慶應に出たボールを、浅田は何のためらいも見せずハイパント攻撃にした。狙いは早稲田FBの石井だ。合わせるのは7番玉塚だ。
「いけっ」
と、浅田は叫ぶ、玉塚の背が、踊るようにして石井に肉迫していくのが見える。己の蹴った球が、どんな飛行線を描いているか、という思いがちらっと頭をかすめたが、石井の姿を追って駆けた。
石井が捕った。と、そこへ玉塚のタックルが入った。思わず球をこぼす石井勝尉。
「ここは必ず田代か玉塚が入る。そして球がこぼれ出てくる。そう思っていました」
若林俊康はそう言った。
どよめきと歓声が起きたのはこの時だった。こぼれ球が石井の左を転々とした。その球に豹のような素早さと精悍さで飛びついた男がいた。若林俊康であった。若林は右に開くと全速力で駆けた。完全に走り勝つ。それが若林の使命だった。
だが早稲田にとって、このまま若林に走られてはゲインどころか、ゴールすら割られかねない。冗談ではなかった。吉川、土肥らが必死に戻る。追いついた。そして若林をなんとかラインの外へ押し出すことに成功した。
「私がこの試合を見られないと決まった時、私は上田監督と綿密な打ち合わせをしました。どんな戦い方をするか、早稲田の出方をどう読むか、それはもう必死でした。その結論の第一は、フォワード戦に打ち勝ち、ここ一発というとき、松永、林、若林で奪るというものでした」
堀越慈は沈着な男である。言われたことはどこまでも守ろうとする。約束は滅多に破らない。またチームにとって強い味方となる抜群の記憶力とラグビー理論の深く鋭い展開がある。彼の野太い声で一喝されると、並みの新人なら縮み上がってしまう。加えて母校慶應に対する愛情に燃えている。
その彼が晴れの早慶戦を見ずしてヨーロッパに旅立つというのである。堀越慈は何も語らない。
32分、真下レフェリーの笛が鳴った。
早稲田がラインオフサイドを犯したのだった。このPGを浅田は難なく決めて、6対4とした。
再び激しい攻防が始まった。戦線が正面スタンドよりに移動した。と、その時である。芝生に陣取っていた医師団から、なにやら声がかかった。真下レフェリーはプレーを中断させた。医師団は慶應FLの田代の動きが不自然だと警告した。田代がグラウンドの外に出された。脳震盪の疑いがあった。
石井は田代の一時退場を見逃さなかった。ラグビーは陣取りゲームである。と同時に、数のゲームでもある。いま慶應は一人足りないのである。この時に1メートルでもゲインしておくのが常識である。
石井は飛距離のでるキックで前進した。大きなゲインであった。早稲田はラックを支配する。早稲田ボールのスクラムが命じられた。そこへ田代が復帰した。大したことはなかったようだ。「わーっ」とあがる歓声。頼りになる男が帰ってきたのだ。それが観客席にも伝わった。
ボールが入った。松尾が下がる、と、もうその瞬間に田代、玉塚のFLが勢いよく飛び出していた。その飛び出しにプレッシャーを感じたのか、早稲田バックス陣は、じりっじりっと後退を余儀なくされた。後退につぐ後退である。しかしなんとか態勢を立て直すと早稲田は反撃に転じた。
「この攻防は前半の山であると感じていました。ここを凌げばなんとかなる。逆に、やられたら、するするといかれる。そんな大事な場面でした。」
そう言うのは上田監督である。
「万事休す」
と思わず上田監督が腰を浮かすような場面が、次に現出する。
慶應がオフサイドの反則を犯したのである。
37分、もう前半の残り時間は少ない、ここで確実に3点をもぎ取り、7対6とリードして終わりたい。早稲田がそう思うのは当然だ。狙うのは吉川である。吉川は慎重にプレースした。どこにも緊張のないスムーズなキックであった。しかしボールはポールを割らなかった。
「僕のキックが不調であった。それは認めます。でも自信はあったのです。あの位置なら確実に入る自信が。でも外してしまいました。言い訳なんか通りません。あれさえ入れていれば、そう思って今でも歯を食いしばっていますよ」
吉川はそう言う。口惜しさは一生消えないであろう。しかし、取り戻す手はある。
前半の残り時間が少なくなってきた、早稲田は仕掛けなければならなかった。
「さあ、やるぞ」
そう森田は目で合図を送る。吉川も、土肥も、石井も、目でうなずく。もうキックはしない。あくまで手と足で、慶應陣深く突き刺してくれる。早稲田バックス陣は、そう決意する。
森田がボールを持って出た。吉川がいい位置に上がってきた。ポンポンとボールがバックスに渡った。
「よこせ、俺に」
そんな叫び声が聞こえそうだった。石井勝尉だった。FBの通常のライン参加ではあったが、大型FBの突進はそれだけで威力があった。
タックル!誰が入ったのか、一瞬見失うほど鋭い飛び込みであった。林千春だ。
早稲田の攻撃はそこでとまった。
「地を這うようなタックルを決める、それが真髄なんです。だが、姿勢はなかなかとれない。相手の足下だけを見ているというのです。でも、身体が自然と浮き上がってしまいます。これをなんとか克服して、今日の試合に臨んだのです」
堀越慈は今そう言う。
一進一退の攻防が続いていた、しかし、この攻防が、前半の山場を過ぎた余波にしか過ぎないことを、観客は知っていた。慶應側にこぼれた球を生田が蹴りだした。球がタッチを切った。レフェリーの笛が鳴った。ハーフタイムだった。
「よし、このままでいける。後半に入ればスタミナがあるのだから、俺たちのもの前に出て勝負だ」
そう上田監督は言った。しかし、慶應フィフティーンは、誰もこの言葉を覚えていなかった。
「勝負はこれからだ。早稲田のラグビーをすればいいのだ。しっかりタックルし
ていこう」
簡単なことを日比野監督は言った。フィフティーンは、おおっ、と声に出してうなずいた。
松永の母、冨美代は、息子の姿を慶應の円陣のなかに見出していた。敏宏は大阪、天王寺高校時代に、ラグビーに取りつかれた。ラグビー一色だった生活から、一年の浪人生活を送って、京大に合格した時、これであの子は、今までと違う青春と人生を送ると思った。しかし、それでいいのだろうか。母は息子の青春というものを根本から考えてみた。
「お母ちゃん、僕、慶應も合格してん。どないしよう。」
母は、きたっ、と思う。一年の浪人生活でうっくつした肉体の不燃焼感は、もう爆発寸前であったに違いない。天王寺高校時代、全日本高校選抜にも選ばれている敏宏だ。このまま京大へ入学して、それなりのラグビーをやるか。慶應のタイガージャージを着て、思う存分暴れまわるか、敏宏の心は、ちぢに乱れているに違いなかった。
「敏宏、もう一度ラグビーやったらどうや。学問は年取ってからでもできんことはない。けど、ラグビーは若い時だけやで。もし今判断を間違えたら、一生後悔するかもしれんなあ」
と、母は言った。
この母の一言で人生が変わるというほど、松永が母の言いなりになる男ではない。だが、進路を選ぶのに随分と気が楽になったことは、事実だろう。
自分のアドバイス、そして息子の判断、両方とも間違っていなかったと、今母は思う。
「敏宏、思い切りグラウンドを駆けるのや。悔いを残したらいかん」
母は祈るようにして呟く。と、その時。試合再開の笛が鳴った。
「選手たちは冷静でした。後半、絶対いける。そんな確信をもちました」
上田監督は後にそう語る。しかし、ハーフタイムの指示を終えて戻ってくる顔には、そんな確信を表す表情など、上田監督のどこにもなく、への字に結んだ唇はあおざめてすら見えた。
「簡単に勝たせてはくれません。どこの大学も懸命なんですから。多くのことはいいません。早稲田のラグビーをしようということでした」。日比野監督はそう言う。
試合さいかいは、早稲田のキックからであった。
「キックが悪かったと言われるのですが、僕と森田、石井、が蹴ったキックはそんなに悪いとは思っていませんでした。ただ、僕の蹴るゴールキックが入らなかった。これは・・・。ですから、この試合再開のキックは慎重にいいところに落ちるように、蹴ったものでした」
吉川はそう言う。
村井は待っていた。吉川が蹴り上げてくるであろう位置を冷静に読んでいた。その読みは正確だった。ボールがきた。村井はしっかり掴むと大きなストライドを飛ばして、早稲田陣に蹴り返した。ほーっという声がスタンドから洩れた。
早稲田ボールのラインアウトであった。
早稲田は通常のラインを敷く。米倉のスローイングに合わせ、ボール奪取に跳ぶ栗原。タップされたボールは松尾からSO森田に渡った。
「ここはぜがひでも走りたかった。縦について慶應のディフェンス陣を、僕に引き付けておきたかった。そうしたら、吉川でも、土肥でも、仕事がしやすいと思ったからです」
森田はこの時、自分の最も得意とする左足キックを封印して、走ることに専念したのであった。しかし、慶應のFL陣は、森田博志の意図した縦突進を自由にはさせなかった。
森田の内に切れ込んでくるような攻撃を、ゆっくりと止めていたのではなんいもならない。一歩も二歩も早く敵陣に飛び込んで、芽の出ないうちにつみとる。慶應のディフェンスはそうでなければならない。
「早稲田にバックスは、執拗に球を活かすでしょう。まるで、とりもちのように、球をつなげてくる。それを阻止するには思い切ったタックルを浴びせ、球を奪い返す、それしかないわけです」
堀越は、早稲田バックスの特長を、そんな風に言う。
各大学とも、この早稲田バックスの粘りに、苦杯をなめさせられているのである。
「慶應はこれしかないのですから、僕らはちっともうまくないのですから。ただ、不器用にラグビーをやるしかないのです」
そう言うのは東山勝栄(昭和55年度主将)である。
東山らの代は早稲田と引き分けている。その勝負も大学ラグビー史上、長く語られるものであろう。試合の中身は、東山が言うように不器用な慶應フォワードが、押しに押して引き分けたものであった。
慶應の伝統は、基本に忠実に、試合に臨むことであった。そこには、なんのてらいもなく、常に淡々としているかのようであった。だが、その闘魂はいつも燃えていた。それが誰にも見えないために、慶應のラグビーが透き通って見えなかっただけである。
うららかな日和にさっと影がさした。絶好のコンディションであったが、この陰りがどちらかに味方しないで欲しかった。
早稲田はハイパント攻撃に的を絞った。村井の頭上に上げられるパント。尾形、山本、清水らが追走する。村井が補球するが、キックする余裕がない。ずるっ、と後退する村井。
「放れ!」
そう叫んだのは若林だった。若林は村井の右斜め後方にいた。
「頼む、わか」
村井はためらわず若林に後をたくした。
これを見た早稲田フィフティーンは。若林の足を警戒して、左サイドに気を取られた。走らせてはいけない。そう思った瞬間、若林へのディフェンスが甘くなった。
しかし、若林は無理をしなかった。バックスタンドよりのタッチラインめがけて、思い切りのいいキックを蹴り上げていた。
「わか、サンキュウ」
村井は手を挙げてそう言った。
主将松永が倒れた。もともと左太腿部に肉離れを負っている。その上なにか負傷でもしたなら、致命傷になりかねかなった。
「立て、立ってくれ。貴様が立ってくれなければ、この戦況をどう判断して組み立てるのだ。さあ、立て。松永、立て」
グラウンドに散らばる慶應の14人は、等しくそう思っていた。なかでも村井は、すぐさま飛んでいき、傷の具合を尋ねたかった。
「あれは日体大戦を迎える1週間前だったと思う。おれたちは万全を期しただろうか、何かし残したことはないだろうか、そう言いあったことがあった。みんなの気持ちが緩んでいたとはおもえないけど、こんあもんでいいのでは、という気持ちになって、禁酒も、禁煙もしないでシーズンを送りそうになった。その時、お前は泣いて怒った。あれでおれたちの目が醒めた。おれたちのまとまりを待っていたお前が、ついにしびれをきらしたんだな。酒を断って全試合に臨む。そう言って俺たちを、お前は引っ張ってきた。さあ松永、仕上げじゃないか。立って、おれたちを引っ張ってくれ」
そう村井は言い続けた。
松永は背を丸め、苦痛にたえていた。だが、やがて大きく息をつくと、みんなの待つ戦線へと戻っていった。
5分過ぎ、メインスタンドより、やや慶應陣に入ったところで慶應が反則した。スクラムの中で手を使ったという反則だ。
ここは、絶対に狙っておかなければならない。しかし無情にもこのキックは外れてしまう。かつてのキッカーの誰それなら、なんなく決めていたであろうという言葉は、吉川には酷であろう。
「このキック絶対に決めるのだ、また絶対に入るのだ。そう思って誰だった蹴るのです。しかし、外れることはしょっちゅうあるわけです。あのキックが、1本入っていたら勝てたという勝負は、過去にいくらでもあります。あの大観衆の中で、動ぜず蹴ることができるようになるには、肉体的訓練はもちろん、精神的訓練が欠かせないのです。それを若者に完全要求することは、とても」
そう言うのは小藪修(元新日鉄ラグビー部監督)である。
気を取り直したかのように、早稲田は戦線を組み直した。
「慶應にやられっぱなしでは早稲田のフォワードとして、情けない。やつらがやってくるのなら、よしこっちからもしかけてやろうじゃないか。そんな気になっていましたよ。ほんとに血が踊っていました」
尾形はそういう。
スクラムがまわった。崩れかかった。ラックになりそうな気配がした。慶應が支配したかに見えた。が、こぼれた。そのこぼれたボールを早稲田のFL陣が蹴った。球は慶應のディフェンス陣の間隙をついた。
「よし、ここだ」
尾形は腰を低くして前進した。目標は前方に転がる球だ。こいつは絶対俺が捕る。捕ったらまっすぐ走るから、誰でもいいからついてきてくれ。
尾形の後ろには清水がいた。そして主将の矢ケ部がついていた。
慶應のディフェンスが対応できない。つぎつぎに戻ってくるが、早稲田のフォワード陣の突込みが強く、そして速かった。
10分過ぎだった。尾形がつかまった。もうここまでか、と思った時、清水がフォローした。雪崩をうって慶應陣に突入する。清水もとまった。矢ケ部がいった。7万の観衆が息を殺す。
信じられない早稲田フォワードの粘り強さである。だが3人のフォワードラッシュを成功させれば、もうこれだけで十分なゲインを達成したものと思われた。しかし、早稲田は追撃の手を緩めなかった。
「あいつ、憎らしいほど成長しやがったですね。あそこまで走りこんでいたとは」
そう言うのは平島健祐(昭和59年慶應卒、LO)だ、平島の言うあいつとは、弟の平島英治のことであった。
11分、その平島英治がきた。矢ケ部からボールをもらった地点は、ゴール直前5メートルだ。2歩、3歩と走る。しかし死守しようとする慶應守備陣が、横殴りのタックルをかける。もうここまでであった。平島英治はローリングするようにして倒れこんだ。
トライ!
真下レフェリーの手があがった。平島英治のトライは、早稲田フォワードの執念の帰結であった。
「あの試合、僕はタッチジャッジをつとめたのです。そして、その時感じたのですが、タッチジャッジはプレーするより、疲れるものでした。最初、尾形が行きましたね、その動きに合わせて僕も走りました。行ってくれ、どんどんもちこんでくれっ、そんな気持ちでした。彼らは本当によく走りました。」そう言うのは佐々木卓である。
20分、激しいラックになった。両軍とも相手を下からめくりあげようと、低い姿勢からラックに飛び込んでくる。慶應の中野がいく。早稲田の恵藤が入る。慶應一列の五所、橋本が支える。そこへ早稲田プロップ尾形が割ってはいる。その集散はわずかに、慶應が速い。
ピッ、と笛が鳴った。
早稲田オーバーザトップの反則をとられたのだ。
「こんな場合、どうしても飛び込んで反則になってしまうのです」
そう言うのは笹田学である。
相手より一歩でも早くラックに飛び込み、ボールに接近し、掻き出そうとする。そのために犯してしまう反則なのである。
しかしこのPGを浅田は外してしまう。
「入れておきたい。そう思っただけでプレッシャーになりました。どんなキックでも、かならず入る、そう思って蹴るのですが、残念です」と、言った。
私は、山中湖の合宿で、浅田の雄姿を写真に撮らせてくれと頼んだことがある。しかし、今のトレーニング不足の姿を見せたくないと、浅田は頑なに拒んだ。私は、私の瞼に残る、浅田武男のキックする姿こそ、すべてであると思い知ったことである。
24分、若林が右にもって出た。スワーブというには、あまりにも大きな回り込みだった。しかし、早稲田のマークを外すにはそれしかなかった。右方向に大きな穴がぽっかり空いた。若林俊康はスピードを上げた。バックスタンド沿いに一直線で走った。その時、若林の視野に、相手FBの姿が入った。
「こいっ」
若林はそう腹の中で呟く。きたっ、石井だ。石井の形相が変わっていた。細い目がこめかみにまでとどきそうであった。距離はさらに縮まった。左にステップを切って抜こうか、と思った。と、その瞬間、石井の両手が若林の体をタッチの外へ放り出していた。
石井はタックルにいかなかった。タッチに押し出すという最も安全な方法をとった。
「あそこでタックルを一発かましておくべきだった。早稲田の最後の砦には石井がいるって、そうあいつに思わせておかなければならなかったのです」
その最も安全で落ち着いたプレーが、石井と若林の間に心理的なギャップを広げることになっていく。
「僕に振り切られたらトライになるかもしれませんが、それを覚悟でタックルに入られたら、ちょっと次の攻撃の時に、同じコースを走ったかどうか、それはわかりませんね」
と、若林は言う。
慶應首脳陣は、若林の快走を見て、ある予感を抱く。
モール・ラックをこの調子で戦い続け、攻めてさえいけば、かならず早稲田陣のどこかに穴が空く。その時、若林の足が活きる、と予感したのである。
慶應が再び攻め込んだ。早稲田が防御に戻る。ラインの外へ外へと追うディフェンスが功を奏して、辛うじてタッチに出した。
慶應にとって、ここは押せ押せのムードだ。ラインアウトをとって、一気に攻め込むのだ。そんな意気が感じられた、玉塚が投げた。
「ねらっていたなんて。でも敵ボールを奪りたかった。そこへ絶好球がきたんです。びっくりしたですよ」
そういうのは栗原である。
栗原は、慶應スローワー玉塚の投げる球を、すっぽりという感じで捕ると、腹に抱き込み、SH松尾にたくした。
「あれはまずかった。栗原が前で両手を上げているので、いつも後ろに投げて勝負していたのですが、あの時だけは裏をかくつもりだったんです」
と玉塚は言う。
早稲田は左に攻撃を展開した。しかし、この展開に対応した慶應の守備陣は、各自の責任分担を明確にし、全うしようと、果敢に前に出てきた。
松永が行く。市瀬、村井が上がった。FL陣がひたひたと肉迫していた。たちまち混戦状態となった。ボールを追っている者にあたりをつけてぶつかっていく。激しい、あまりにも激しい当たりだ。
笛が鳴った。慶應の反則だった。
これは誰がという反則ではない、混戦状態の中では仕方のないように思えた。
しかし、そこは早稲田にとって、PGを狙うのに絶好の位置となった。
「もう外せません。これを外したら、東伏見に帰れません。そんな気分でボールをセットしました」吉川は言う。
日比野監督の表情はその時、やや蒼ざめてみえた。このPGを入れるか外すか、この後、十数分の試合展開に、大きな影響を及ぼす、この時までの得点は、早稲田8点、慶應6点であった。2点のアヘッドを守るより、ここでPGを決めて5点のリードで戦いたいと願うのは、当然であった。
「楽に勝たせてなんかくれませんよ。どこの大学だって一所懸命なんですから」
これは日比野監督がよく口にする言葉である。
昭和59年の菅平合宿で、早稲田フォワードの充実ぶりをほめると、言下にそれを否定した。そして、仕上がって欲しいと願っているが、苦しい戦いを覚悟していると言った。
まさしく、その言葉通りの苦しい戦いであった。
いったい、どこに死角があるのだ。慶應の穴はどこにあるのだ。日比野弘は、それを天に、地に、風に、雲に聞いてみたい心境であったろう。
だが、この時、ほんの微かな光明が見えた、それは、吉川の右足だ。これなら確実に3点は稼げる。そのためには、何としてでも敵陣で戦わなければならなかった。
吉川がスタートを起こした。
「入ってくれ。そう思って握るフラッグに力が入りましたよ。」
そう言うのは佐々木卓である。
吉川の蹴ったボールは左へ左へとカーブした。ああっ、と声が早稲田ベンチに上がる。切れる、誰もがそう思った。と、その一瞬だった。ボールは左ポールに当たった。
佐々木は、そのボールが今度は反転して、左へ切れてくるのを見ていた。
「入った。そう思うと肩の力が抜けていくようでした」
佐々木は高々とフラッグを上げた。
これで11対6となった。早稲田首脳陣は全員大きな溜息をついていた。
もう残り時間はどれぐらいだろう。国立競技場の大時計とレフェリーの時計とでは、かなりの開きがある。したがって、大時計があっても、あまりあてにはならない。ちせは、後半も半分が過ぎたなと思っている。
「スタミナという点では、まったく問題なかったです。まだ十分余力が残っていました。ただ、僕のポジションなんですが、初めて左のWTBに起用されたものですから。そっちの不安がないとは言えなかったですね」
市瀬に得点を期待してWTBに投入したというより、早稲田の攻撃をきっちり摘み取って欲しい、という願いで上田監督が入れたものであろうと思われた。その重責を市瀬は見事に果たしていた。
小野寺孝(慶應ラグビー部コーチ)は、慶應の15人一人一人を見ていた。走り方、息のつぎ方、モール・ラックへの入り方、ボール位置への集まり方、どれをとっても、早稲田に引けを取っているものはなかった。
小野寺は、早くからラグビー選手の肉体づくりを提唱していた。それには苦い自らの体験があったからである。小野寺は大学4年生の時、怪我をし、そのシーズンを棒に振っている。立派な肉体はそれだけで、ゲームをしやすくする。また怪我もない。ゲームが楽しく、そして怪我がないとなれば、試合結果はおのずと良くなるのは当然であると考えたからである。
「さあ見せてくれ、慶應ラガーメンの出来上がった体を」
そんな誇らしげな気持ちで小野寺は胸をはった。
30分だった。慶應が執拗に攻め込んでラインアウト、そこで早稲田の反則、バージングを引きずり出した。
浅田は、ゴールまでの距離をはかると、狙わずハイパントを上げる作戦をとった。
例によって浅田は、足でひょいと調子をとると、ボールを高く蹴り上げた。絶好の位置に上がった。
そのボールの落下位置へ、柴田、中山が駆け込んでいく。落下位置には清水と栗原がいる。栗原の視野に二人の姿がはいった。ボールは確かに取った。しかしふたりがかりでボール奪取に燃える柴田とバイスキャプテンの中山は、二人の腹に当たっていった。清水と栗原はたまらず横転した。
二人はすぐに立ち上がれなかった。栗原は軽い脳震盪をおこしていた。早稲田ボールのスクラムとなった。これを素早く出して、吉川がタッチを切った。ラインアウトは早稲田が最も得意とするところであった。これをしっかり捕って、松尾にパス、松尾はそのままサイドを走って、縦にキックを上げた。判断のいい攻撃だった。これに慶應は幻惑された。
球がこぼれている。両軍バックスの頑張りどころとなった。浅田が拾った、と、森田が目前まできていた。もうここまでだった。浅田はタックルを受けながら、村井にボールを託した。
一刻の猶予もならなかった。村井は戻りながら、バックスタンド方向にキックした。タッチに蹴りだすには、少し距離がありすぎた。なんとかオンサイドの味方選手が走りこんでくれることを願うしかなかった。
橋本は、自分の位置が、オフサイドではないことを知ると、村井の蹴った球を、ひたすら追った。早稲田センター鈴木が追いつきそうだった、が、ファンブルした。その一瞬の間合いに、橋本のタックルが決まっていた。
たちまち慶應の支配するラックになった。
「絶対こっちに出る。それは確信でした。出たら、左に攻めるか、右を突くか、これは勝負でした。結局、ブラインドを突いたのですが、今までなんども形になっていた若林の攻撃が、もう成功すると判断したのです。でもトライになるとは思っていませんでした。もう一つか、二つの布石があってどうにかなる、そんな気がしたのです」
生田は今、そう語る。
若林は素早いバッキングアップで、バックスタンド寄りに上がってきていた。
「今だ、放れ」
と、若林は叫ぶ。
生田は振り向きざま、ほとんど真横に伸びるパスを送った。この攻撃感覚は並ではなかった。冒険と言ってよかった。早稲田フォワードの待ち受けているサイドを駆け抜けるには危険が多かった。そこには出足のいいFL矢ケ部、平島、恵藤らがいる。そして最後の砦として石井勝尉がいる。またタッチラインという、もう一人のディフェンダーがいる。
だが、あえてそのコースを生田は選んだ。そして若林は、待ち受けているであろう早稲田FL陣の中へ突入していった。
矢ケ部が来た。顔を見た。まなじりを決したいい顔だと若林は思った。邪心のない、澄み切った顔をしていた。
矢ケ部のタックルがきた。若林は辛うじて左に踏み込んだ足を持ちこたえた。
矢ケ部のであしが鈍かったのではない。生田、若林の仕掛けが一歩速かっただけである。その差は、矢ケ部の届かぬタックルとなった。だが、若林もよろける。
「あっ、危うい」と誰もが思った。なぜなら、その時、若林は転倒しそうになったのである。が、辛うじて態勢を立て直した。
次は平島だった。彼はトライをとって気分がのっている。こんあ相手はうるさい。幸い矢ケ部より位置が深かった。それだけ若林に届くには辛い位置にいた。それに、つんのめるように若林が体を泳がせたため、平島のタックルポイントがわずかに狂った。
「かわした。そう思ったのです。しかしもう一人難関が待ち受けていました。それは石井でした。もう何度も対決しているのですが、ここ一発は、かならず僕をとめていましたからね。この時しかない、さあいくぞ、という気になりました。」
31分、若林は駆けた。おのれの体が獣になったように感じた。若林はタイガー軍団の名に恥じない奏者でありたかった。
石井がきた。これまでなんと憎い奴かとおもっていたが、その思いはもうない。自分の体全体が不思議な透明感に包まれていくのを、若林は感じていた。
歓声が潮の満ちる音のように緩慢に聞こえた。ゴールラインは船から見る水平線のように揺れて見えた。それもごく近くに揺れて見えたのであった。
またひとしきり、潮鳴りが聞こえたように思った。
若林は石井を振り切ったのを知覚していなかった。どこでどう振り切ったのか、それは無意識のまま、抜き去ったようであった。
ゴールラインを超えたのは知っている、回り込んだのもわかっている。そして、今タッチダウンしたのも覚えている、だが、それから数秒間のことを、彼はまったく思い出せないのだった。田代がきた、玉塚も来た、そしてポンポンと頭を殴ってくれた。本当にたくさんどやしつけてくれた。それで彼はやっと正気に戻った。
トライしたんだ、トライしたんだ!
浅田は冷静だった。絶対入れなければならない、そう思うのは当然だった。若林が、自分の蹴る距離を考えて、走れるだけ走って、稼いでくれたのだ。この位置なら大丈夫だ。任せておけ。必ず入れて見せる。浅田はそう思う。
浅田はポンと右足を蹴り上げると助走に入った。このキックがどんな意味をもつものか。それを両軍の首脳陣は、熟知していた。
「試合の流れから言って、慶應になにかが傾きかけていました。このトライが、それを決定づけました。しかし、トライだけではリードしたことになりません。落ち着いてコンバートっすることがどうしても必要だったのです」と小野寺は言う。
浅田はキックした感触をしっかりと覚えている。蹴った瞬間、入ったと思った。PGやGKを狙うキッカーなら、当然入れておかしくない位置であった。それだけに重圧はあった。確実にとれるものはとっておく。そんな自明のことがラグビーでは難しいのだ。
ボールはやすやすとバーを越えた、これで12対11.慶應が逆転に成功したのだ。
観衆は絶叫した。「ワセダ」「ケイオウ」とただ大学の名を連呼するだけだ。ほかにどんな言葉があるというのだ。その一言ですべてが足りた。
引用させていただいた馬場信浩氏の観戦記は続くが、慶應はこの試合に勝利し、対抗戦全勝優勝を果たした。
この試合を見た者は、「若林の逆転トライ」を末永く、後世に語り継いでいる。