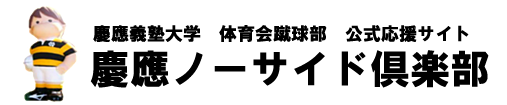蹴球部創部百年目の大学選手権優勝
(1999年4月→2000年1月)
(世田谷の塾員編)
慶應義塾大学體育會蹴球部は、1899年晩秋、ケンブリッジ大学出身のエドワード・ブラムウェル・クラークとケンブリッジ留学経験を持つ田中銀之助の指導により産声を上げた。
それは同時に、日本ラグビーの黎明でもあった。1999年度、すなわち創部百年目のシーズン、慶應は、長い低迷を脱して、大学選手権優勝を達成した。この記憶を、記録に基づいて振り返ってみよう。以下、
『慶應ラグビー 百年の歓喜』(生島淳 著 文芸春秋刊)より引用させて頂く。
慶應は(中略)シーズンに突入した。初戦はケンブリッジ大学との招待試合であった。
この試合、観衆を唸らせたのはFBに入った栗原徹だった。英国の伝統を栗原は翻弄した。相手に指一本触れさせなかったのではないかと錯覚させるステップ。後半11分、FB栗原、ケンブリッジのディフェンスを引き裂く「電撃の」トライをあげる。今シーズンの慶應は何かやってくれそうだ。秩父宮の観客は、この瞬間、きっとそう感じたはずだ。
この日も山中湖同様、ラグビーにとってはあまりに季節外れの猛暑だったが、創部百周年の秋、慶應はOBをわずか3人だけ入れただけのメンバー構成になった。それだけに、このシーズンを占ううえで重要な一戦といえた。結果は42対21.試合は終盤までもつれたものの、結果的には慶應の圧勝になった。記念すべきシーズンの、幸先良いスタートである。FWのサイズはさすがにケンブリッジには劣るものの、この分なら日本の他の大学チームに劣ることは稀だろう。BKも栗原を筆頭に、個人能力の高さが目についた。
ただし課題もチラホラ目についたのは事実である。FWで言えばラインアウトの精度、スクラムサイドのディフェンス、そして夏前から積極的に取り組んで来たモールの整備にはまだまだ課題が残っていた。しかしこの弱点も11月にはすっかり修正されていた。BKはユニットの働きが薄く、肝心なところでパスがぶれた。この点はシーズン終盤になってもなかなか改善されなかった。しかしこの日ばかりは、楕円の気まぐれは慶應に味方した。
タイムアップ。日陰でストレッチする選手たちの中に、一昨年の主将、田村和大の姿があった。現役時代と変わらない屈託のない笑顔がこぼれていた。彼はいかにも慶應らしい叱咤激励タイプの主将だった。
「本当は後半もプレイしたくて、上田さんにお願いしたのですけれど、駄目でした。体が小さい僕がこんなにできるところを現役の部員に見せたかったんですけれどね」
先輩キャプテンに、9月時点で、高田主将のリーダーぶりはどう映っていたか。
「最初は遠慮していたみたいです。先輩もいましたからね。でもアイツはプレイで示す男ですから、大丈夫。これからキャプテンとして良くなっていくと思います」
ケンブリッジ戦の翌日、三田にある慶應の校舎で百周年の記念式典が行われた。列席者に三笠宮妃殿下、鳥居泰彦塾長、駐日英国大使などの顔が並ぶ。
式典に続き、三田校舎の中庭で、記念イベント。幼稚舎から大学まで、すべての慶應ラグビー部の面々、遠来のケンブリッジ、長い年月にわたり鎬を削ってきた早稲田、明治のOBの顔ぶれも見える。
突如、ケンブリッジのメンバーがステージに上がり、美声で歌い始めた。中庭に轟く朗々とした歌声、そして慶應の歌の返礼。ケンブリッジが歌い、慶應が続く。
ラグビーの魅力、勝負の後のビールが、歌が、交流が、人間を成長させる。
この会の締めくくりは、高田キャプテンソロではじまる部歌の合唱。キャプテンソロこそは、ラグビーのキャプテンシーの象徴だ。
「白皚々の雪に居て~」
慶應のOB、学生が一体となって彼の歌声に続く。ケンブリッジの学生も居住まいを正す。
刹那、名門校のキャプテンとは孤独であるが、それでいて何と遣り甲斐のある「仕事」なのだろうと思った。マニュアルなんぞ、あるわけではない。練習メニュー、メンバーの決定、そして社交の場での顔。誤解を恐れずに言えば、早稲田、明治、慶應のキャプテンの仕事は、極東一国の首相の仕事よりはるかに価値があり、尊敬に値するように思える。それを22歳の若者が務めるのだから、恐れ入る。
そして9月15日、秩父宮で東大を相手に慶應の対抗戦が開幕した。シーズンが始まってしまえば、日曜日に試合が終わり、その瞬間から次の対戦に向けた1週間を迎える。その準備が繰り返される。
対抗戦開幕後、慶應は順調に白星を積み重ねた。
〇東大戦 129対5
〇青学戦 99対0
〇筑波戦 57対19
初めて骨のある対戦相手である筑波大に圧勝し、対抗戦の優勝争いは慶應を軸にして展開されることが予想された。続く第4戦は、10月24日の日体大戦である。ここまで両者とも全勝である。戦う集団は1週間をどのように過ごし、試合を迎えたのだろうか。ここに彼らの「普通の1週間」を見ることができる。
10月18日、東京築地、聖路加国際病院。
この日、1階の受付でコーチの林と待ち合わせた。彼が前日の筑波戦で怪我をした栗原に付き添うため、急遽、病院での待ち合わせとなったのだ。
57対19。スコアだけ見れば慶應の圧勝だ。しかし時としてスコアは事実を伝えきれない場合もある。ラインアウトは安定せず、密集付近での反則が目立ち、テンポも悪い。それでもこのスコア。監督の上田昭夫の言葉がここ数年、慶應に起きた変化を的確に表現している。
「昔はこんな試合していたら負けていたんだよね。逆のスコアでさ」
しかし好事魔多し。栗原がカウンターアタックの最中、視界の外からタックルに入られ、腓骨を痛めた。前日に運ばれた病院では3人の医師がレントゲン写真を見ながら、骨折だ、いや違う、という議論になったという。しかし結論は出ず、栗原が昨年腓骨を骨折した時にお世話になった聖路加病院の医師の診断を仰ぐことになった。
車椅子から松葉杖に移動手段を変えて、レントゲン室へ向かう。そして診察。30分経っても出てこない。もしや・・・不安がよぎる。やっと2人が現れ、林が恐縮しながら言う。
「もう1回レントゲン撮ってきます」
そして昨日はみつけられなかった決定的な証拠が発見される。やはり腓骨の骨折。全治4週間。慶明、早慶戦には間に合わない。こんな時、かえってこの場に居合わせた自分を呪うことになる。かける言葉は、そう簡単に見つからない。
「これもいい経験ですよ」
沈黙を破ったのは栗原の方だった。栗原本人は淡々としている。部外者を前に自制心を発揮しているのか。ただ次の一言には無念の思いがこもっていた。
「明治戦、出たことないんですよ。明治っていうと八幡山のゲームのイメージしかないんです。でもまあ、正月には間に合いそうなんで」
1年生からエースだった。しかし3年生になった今も、ビッグゲームでの登場機会は1年の時の早慶戦のみ。豊かな才能を持つ若者のキャリアは決して順風満帆ではない。
病院で一番辛そうだったのが林である。彼は、言葉を絞り出すようにして、呟いた。
「残念だなあ」
彼も言葉が続かなかった。時として沈黙は言葉よりも、重い。
翌10月19日、横浜・日吉、慶大蹴球部合宿所。
12時。一昨日ゲームに出ていた選手たちが集まってくる。林の顔が心なしか腫れぼったい。聞けば、昨夜は午前3時まで主将の高田とビデオの分析をしていたという。高田が林の自宅に泊まることはもはや日常化していた。
この日選手たちが集まったのは、試合のビデオを見てプレイの評価をするためである。内容はタックルの成功・不成功や、攻撃パターンの効果の判定をしていく。面白いのは攻撃地点ごとのアタックの成功率。例えばポイントに近いところをチャンネル1、やや離れたところをチャンネル2、展開した場合をチャンネル3と規定し、チャンネルごとの効果を調べる。青学戦でのチャンネル3の成功率は100%だった、
分析は、プレイごとにビデオを止めて行われる。時々スローでじっくり再生して吟味もする。試合中、センターに入った鈴木孝徳が脳震盪を起こした。ポジションに戻るときもフラフラ。
「おいおい、大丈夫かよ~」
みんな笑いながら冷やかす。脳震盪の犯人は、味方FLの野澤。何のことはない野澤の頭突きが鈴木を直撃、“内ゲバ”で鈴木は意識が朦朧としてしまったのだ。栗原が骨折したシーンでは、林が「外にパス出してればなあ」と残念がる。ビデオは巻き戻せるが現実は戻らない。
全般に和やかな雰囲気で進んでいったが、筑波のトライのシーンだけはディスカッションが活発化した。バックスラインが破られたトライでは、内側からプレッシャーをかけるべき選手の出足が遅れたために綻びが生じたのが確認できる。チームとしてどうすべきか。チームとしてどうすべきか、やり取りが続く。慶應の強さはディスカッションによって育まれた。
ビデオの分析は1週間前まではリハビリ中の選手が担当していたが、この日からレギュラー組によって行われるようになった。ひとつにはビデオでは確認しがたいところでも、試合に出ている本人が見れば解決できる部分が多くあること。それに自分が大胆な反則を犯してしまった場面は記憶に刻まれ、次からは慎重になる。唯一、心配な点は、リハビリの選手のビデオ分析に対するモチベーションが低いことだった。この時期、部内には「下からの」盛り上げは、垣間見られなかった。
この夜、林に上田からメールが届く。日曜日の日体大戦のメンバーの案だ。指揮官、コーチ、主将にはそれぞれの思惑がある。戦い方、選手の特徴が考慮され、翌日の練習までにはほぼメンバーが固まる。昔は選手起用での上田と主将との衝突も多かった。しかし高田組になってその回数は減少しているようだ。イメージが一致してきているのだろう。
10月20日、東京・府中、サントリーグラウンド。
胸を借りる日である。レギュラー陣は揃って夜の7時からサントリーに出稽古。グレーのコートを着た上田の姿も見える。
最初はコンタクトスーツを使って、アタックとディフェンスを交互に行う。
その後、FWとBKに分かれる。この練習の見所はサントリーのスクラム。慶應のスクラムは、学生ではトップクラスである。しかしサントリーにはロックに外国人もいるし、重い。そしてスクラムとはすなわち、経験がものをいう。社会人相手に学生がどこまで組めるのか。ある意味、日本選手権のプレビューでもある。
近場で見ると、まさに骨が軋む激突。寒いので、湯気が立つ。慶應のスクラムが、組んだ瞬間に崩れる。プロップの安龍煥が、「慶應、もっと早く!」と叫ぶ。スクラムは組む瞬間のタイミングが大切だ。後から聞くとサントリーのHO、明治OBの山岡俊が異常に強かったという。久々に見る慶應の劣勢だ。
林の考えでは、このスクラムでの力の差は、経験、体重の他にもスクラム練習の差が出ているかもしれないという。
「サントリーは殆ど生のスクラムを組まないんです。マシンを使って、8人が一体となって掛け声に合わせ、押したり回したりしています。つまりユニットとしての練習が多い。でも慶應は生で組むのが主流なんです。慶應は8人で組むというより、前の3人で組んでいる。掛け声もないから一体ではない。だから当たった瞬間に崩れてしまうんです。」
スクラムの練習を見ると、どうしたって明治戦のことを考えてしまう。昨季1月2日の大学選手権準決勝で慶應は認定トライを献上した。その差は埋まっているのか。結果は意外な形で提出されることになる。
10月21日、横浜・日吉、慶大グラウンド。
日体大戦に向けて練習が本格化する。前日のミーティングで、次の試合での目標が設定された。
敵をノートライに抑えるディフェンス。
相手がキックを蹴ってきた時の連携、コミュニケーション。
ラックでのペナルティを犯さない。
スクラム、ラインアウトでプレッシャーをかける。
ディフェンスに関しては筑波戦で3トライを奪われた。その修正を図ることが目標。具体的にはタックル成功率80%以上を目指す。キックの処理に関しては分析の結果、日体大は筑波戦で相手のキック処理のミスをついて3トライをあげている。そのために慶應バックスの連携をテーマにあげた。また蹴りあいを避けるため、木曜日の練習では蹴り返すのではなく、自陣からカウンターアタックに出る練習も行われた。
最後にあげられたスクラム、ラインアウトといったセットプレイは今期の慶應の強みである。サントリーに苦戦を強いられたスクラムも、学生相手には大きな武器だ。ただここに来てラインアウトに不安が出てきた。スローワーの岡本が筑波戦で左肘を脱臼。そのため日体大戦は前半を岡戸洋介がボールを入れ、後半は野澤が投入することとなった。野澤も投入の練習に余念がない。栗原の怪我は確かに大きいが、岡本の怪我もボディーブローのように痛い。
10月22日、東京・目白、上田昭夫宅。
試合の前々日、慶應の練習は休み。木曜日までに対戦相手に合わせたコンタクト練習を一通り済ませ、休日を挟んで、前日に軽い調整練習が行われる。昨年までは前々日も練習していたが、試合で最高のパフォーマンスを発揮するため今期からはオフに当てている。
この時期、上田は現在高校2年生で有望な選手を発掘するのが楽しみだ。上田のリクルーティングは、一種のアームチェア、すなわち書斎派のリクルーティングである。高校の地方大会には出向かない。いや、出向けないのだ。平日は会社に行き、週末は日吉。予選を覗く時間はない。そこで彼は東京、神奈川、大阪、福岡、長崎といった県大会のパンフレットを取り寄せる。そして有力校の選手のサイズなどをしらみつぶしに調べていく。一見、大変そうだが、未来を開拓する作業だから決して苦にはならない。そして高校の先生や選手と手紙を通じてコンタクトを図る。
一方、慶應志望の高校3年生も正念場を迎えている。湘南藤沢キャンパスのAO入試の願書受付は10月上旬に締め切られ、下旬に一次の発表がある。入学後、慶應ラグビー部に入部希望の選手も十数名受験している。全員が入れる保証はないが、一次通過者に対しては、AO入試を突破してきた現役部員が実際に面接の指導にあたる。まさに部をあげてのリクルーティングだ。
10月23日、横浜・日吉、慶大グラウンド。
早慶戦は一月後に迫った。この日は12時から、リザーブを含めた22人へのジャージの伝達とミーティング。ジャージは上田から手渡される。しかしミーティングが長引いた。上田がかなり厳しいことを言ったようだ。
それはグラウンドの真ん中に場所を移してからの、部員を前にしてのメンバー発表の場でも窺い知れた。(改行削除)上田は部の緊張の欠如に不満を述べた。彼の口調は時折激しい風や救急車のサイレンにかき消されながらも、所々聞こえて来た。
「ウチは強いチームじゃないんだ。努力して強くなるチームなんだ。今の状態はチームとは言えないぞ。試合に出る人間と出ない人間の緊張感に差がある・・・」
段々声が大きくなってくる。
「1月2日の悔しさを忘れたのか。忘れているようにみえるぞ。明治と全勝対決したいからこそ、ここまでやって来たんじゃないのか。だからこそ、明日の日体大戦に緊張感を持つんだ。負けられないんだぞ。いいな。明日の日体大は仮想明治だからな」
その後、FW,BKが一緒になって軽い練習。SOの和田康二が「真ん中遅い!」と叫ぶ。ひとりだけ、試合の時のテンションで練習に臨んでいるように見える。
10月24日、埼玉・熊谷、熊谷ラグビー場。
今季4戦目、日体大戦。前半20分まで嫌な展開だった。慶應が攻め込みながら、時に反則、時にターンオーバーで陣地を戻される。日体大が先制したら分からない・・・。そんな心配を吹き飛ばしたのが、前半20分の野澤のトライ。スクラムからサイドアタック、ポイントから右に展開して和田が内に切れ込み、野澤がそれを拾ってインゴールを陥れた。
慶應はこのトライを境に筑波戦とは違ったラグビーを見せた。69対8。内容を伴った圧勝である。ラックの球出しにテンポがある。攻撃が継続する。スクラムは日体大を圧倒した。野澤、NO8三森の突進は大きな武器となった。センター瓜生靖治は快速ぶりを披露した。この時期から瓜生は急成長し、シーズン終了後にジャパンに入る。ゲームメイカ―の和田の掛け声もすさまじい。怪我の後の復帰第一戦、ゲームに飢えていた人間の叫びだ。
もちろん課題もある。後半のラインアウトはマイボールを確保できず、BKラインを作る遅さが目立った。作っても効果的なサイドでなかったり、ラインが浅く攻撃が展開できないこともあった。試合後和田に球出しに人手がかかったからラインに人がいないのか、それともメイクラインが遅いのか、直接聞いてみる。
「両方ですね。入らなくてもいいところでラックに入ったり、メイクラインの意識が薄いこともあるかもしれない」
反省の言葉が口をついて出るが、試合中とは別人のような柔和な笑顔。この落差こそ集中力があるプレイヤーの証拠だ。
監督の上田もえびす顔を見せる。今日の戦いぶりには満足の様子だ。記者団にコメントを残すと出張なので、とラグビー場を後にする。10月の戦いが終わった。慶應、4戦、全勝。
10月25日、横浜・日吉、慶大グラウンド。
朝10時から、試合に出た選手はアクティブ・リカバリー。試合後の翌日に完全に休むよりも、少し体を動かした方が回復に効果的だというのが昨今の常識だ。
その後、合宿所でビデオを見ながら日体大戦の分析が行われた。新たな戦いへ向けて準備が始まる。いよいよ11月、正念場の季節である。14日には重量FWを誇る帝京大と対戦し、勤労感謝の日には今季スタートから例年に増して素早いラグビーを展開する早稲田が控える。そしてこの早慶戦が、1999年度の大学ラグビーにとって、きわめて重大な意味を持つ一戦となった。
11月に入っても、慶應の勢いは衰えることがなかった。最初の注目の一戦は、7日の慶明戦である。慶應にとっては前年度の1月2日、大学選手権準決勝のリベンジ・マッチである。しかし明治は前週に帝京相手に、早くも黒星を喫していた。
慶明戦の前半は、慶應の動きは硬かった。攻め切れそうで攻め切れない。ゲームは膠着し、8対3のロースコアで前半を終える。しかし後半早々、監督上田昭夫の選手交代で前半はHOに入っていた左座正二郎がPRに回ると、慶應FWは明治スクラムを圧倒し始めた。後半8分にはついにゴール前スクラムを押し込み、上田の記憶にもないという明治相手のスクラムトライ。この瞬間、対抗戦の勢力地図は塗り替わった。このトライで自信を持った慶應はその後もゲームを支配し、慶明戦11年ぶりの勝利を収めた(慶應41対10明治)。
翌週の帝京戦は前橋で行われた。帝京はここまで早稲田に一敗したのみで。120キロを超える両PRが、スクラムに安定感をもたらしていた。しかし課題はスタミナとゲームメイクで、早稲田戦では後半に入ってガス欠状態になり、軽量FWにスクラムを押され、勝負どころでの判断ミスで勝利を逃した。
慶應は帝京FBのキック処理のミスにつけ込みゲームを有利に展開、スクラムではやや劣勢になったものの、危なげなくこのハードルを突破した(慶應31対13帝京)。慶應はついに全勝で早慶戦を迎えることになった。毎年、11月23日に行われるこのカードが全勝対決になったのは、1984年、松永敏宏が主将を務めたシーズン以来、15年ぶりのことであった。
早慶戦に向け、慶應は前日も日吉で最終調整を行い、夕方になった。メンバー、スタッフは品川のホテルに入り、夕食、ミーティング、そしてマッサージなどを受ける。80年代は合宿所から秩父宮に向かうのが通例であったが、湘南藤沢キャンパスに通う選手が増え、合宿所に入る選手が少なくなってから、ビッグゲームの前の日は、全員でホテルに投宿するのがルーティーンになっている。
試合前夜も高田晋作は林雅人の部屋で、ゲームの展開について話し合うことが多い。それぞれの選手もそれぞれの部屋に出向いて話したり、なかには宿題をこなす選手もいる。
意外なことに早慶戦前夜、時間を持て余してしまうのが監督の上田昭夫だった。その夜、上田はパチンコ屋にいた。
「一人でいると、いろいろ考えこんじゃうから、あんまりよくない。テレビを見るのも、落ち着かない。パチンコ屋は考えなくて済むからいい」
その晩の戦績は、予想以上の成果があがった。出る。銀色をしたほんの5グラムの玉が出る。終わってみたら7箱分になっていた。幸先がいいぞ、上田はそう思った。
スポーツ界では、試合前の賭け事を好む人と好まない人が、はっきり分かれる。明治大学ラグビー部の御大、故北島忠治は、早明戦の前夜に上京してきたOBたちと麻雀卓を囲み、四暗刻をつもると、必ず早明戦に勝利したという逸話を残している。上田の場合は、軽い運試しのつもりで、パチンコ台に向かう。勝てば幸先がいい。しかし負けても、彼は気にしない。もし負けていたらどう思ったでしょうね、そう聞いてみた。
「運を貯めたと思ってたよ」
上田は発想の転換が実に素早い。自分、そして慶應にとってより良い方向へ発想の切り替えができる人間なのである。
ロッカールームの雰囲気は異様なほどの緊張に包まれていた。空気は張りつめ、少しでも体を動かすのが、ためらわれた。首脳陣で林が先陣を切って、話を始める。
「早稲田のワイドラインのアタックについては、これはもう十分にディフェンスの練習をしてきてるんだから、しっかりディフェンスしよう。向こうはハイパントで切り崩してくるけれども、ハイパントは向こうがマイボールを放棄しているってことだから、しっかりキャッチしてマイボールにしてアタックする、いいね。それに早稲田は声のプレッシャーとか、いろんなことをやってくると思うけど、全然問題ないからね。惑わされちゃ駄目だよ。しっかり練習してきているんだから、自分たちのラグビーを信じてしっかりしたプレーをしよう。それに今日はキイはディフェンスだよ。今日こそはディフェンスだ。ディフェンス」
ディフェンス、と言った瞬間に林の声のトーンが変わった。それまで努めて冷静に話していたはずだったが、迸る感情を制御できなくなった。それに応えて、選手たちも「ヨシッ!」と絶叫を上げ始めた。林はなおも続ける。
「今日こそはディフェンスだ、ディフェンス!絶対、必ず相手を倒すんだ!倒れたら起き上がって、もう一度倒す。絶対、勝って来いよ!」
ロッカールームには絶叫が響いていた。もう泣きだす選手がいる。
続いては、キャプテンの高田が話す順番である。林と違って、声のトーンが下がり、つぶやくようにメンバーに語りかける。その声は聞き取れないほどである。
「もう何も恐れることはないから、自信持って、しっかりディフェンスして、自分たちの強いところで勝負しよう」
最後は上田の番である。彼はまずメンバーに手をつなぐことを促した。そしてスピーチが始まる。
「いいか、今日のゲームはラグビーじゃない。執念と執念の激突だ。お前ら、自分を信じろ。お前ら、絶対大丈夫だ。お前らには試合に出られない部員もついている。それに我々指導者もついてる。全員で戦おう。お前らに、悔し涙は似合わない。勝って。うれし涙を流せ!」
このスピーチは、このシーズン中で、最も激しいものだった。これより後の大学選手権決勝の時よりも、激しく、情熱的で、人を揺さぶるものがあった。そしてそれをメンバーは怒号で応えた。そして出陣の最後の儀式は部歌「白皚々」の合唱。まずはキャプテン高田のソロから始まる、いつもより、音程が高い。きっと、気持ちの昂ぶりがそうさせたのだろう。
ロッカールームの外では、早稲田のコーチ陣が「先に出しますか」と。相談をしていた。両軍とも、相手より先にロッカールームから出るのを渋っているように見受けられた。林は試合数日前、「ウチは後から出ていくつもりです」とはっきり言っていた。心理戦は、この時から始まっている。結局、早稲田が一足早く秩父宮の歓声に包まれる。
そして慶應側の扉が開け放たれた。それまで漆黒の闇に包まれ、怒号と緊張が支配していたロッカールームに光が差し込み、選手たちはグラウンドに飛び出して行った。こうしてこのシーズンの分岐点となった早慶戦は、キックオフを迎えた。
慶應の心意気を砕くように、早稲田は開始早々から、素晴らしい出来を披露する。99年の早稲田は、決して傑出したチームではなかった。FWは小柄で、きっと正月の花園に出場したとしても「軽量FW」と称されるほど、小さかった。高校生と変わらないのだ。戦略的には98年から採用しているワイドラインを継承、とにかく消耗戦に持ち込み、フィットネスで相手を凌駕する。そして早稲田の選手はこの戦略を何より信じていた。この代表作といえる試合が10月16日に行われた帝京戦だった。
このゲーム、帝京自慢の重戦車FWが前半から早稲田を圧倒、早稲田陣10メートルスクラムから何度も組み直して、ゴール前まで迫ったこともあった。しかし後半20分をすぎると、形勢は逆転した。押し込まれていたはずの早稲田FWが、スクラムで帝京を押し返したのである。信じられないものを目撃したように、秩父宮には異様な唸り声が起きた。早稲田は33対22で逆転勝ちを収めた。以降、筑波戦でも後半30分を過ぎてから逆転したように、前半から相手を突き放す絶対的な強さは持たないものの、久々にきびきびした動きを見せ、90年代に限って言えば、最強ではないものの、最も「早稲田らしい」チームとなりつつあった。
そしてその「らしさ」は、早慶戦の前半、全開する。開始早々の3分に得たPGをSO福田恒輝が蹴りこみ先制、3対0.そして10分、ゴール前で得たマイボールスクラムから、右ウィング横井寛之に展開し、右隅にトライ。
対する慶應は攻め手が少ない。展開しても早稲田の素早いプレッシャーに潰され、チャンスらしいチャンスがつかめない。それでも30分過ぎ、敵陣10メートル付近でペナルティを得ると、ゴール前にタッチで攻め込み、ラインアウトで早稲田をがぶり寄る。阿久根がキャッチ、ピールオフで回り込んできたPR左座正二郎がトライ。和田康二のゴールは失敗したが、11対5と追い上げる。しかし前半最後のプレイで、早稲田は真骨頂を見せる。ラックを連取し、慶應がドリフトで外側にディフェンスがずれるのを見計らったように、CTB高野貴司がゴール下に飛び込み、ゴールも成功、18対5、早稲田リードで前半を終了した。戦前の予想は見事なまでに裏切られた。これで早稲田優位、誰もがそう思っていただろう。
早慶戦のハーフタイム。慶應のロッカーは沈黙の帳が降りていた。いつもは賑やかなロッカールームなのに、誰も喋らない、各々の選手が考え込んでいる感じで、日頃強調されているコミュニケーションがとられていなかった。それぞれの選手達は、ハーフタイムにどんなことを考えていたのだろうか。
主将の高田は、前半の最後でトライを取られたことで展開がちょっといやだな、と思ったが、このまま負ける気はしなかった。
CTBの瓜生靖治は前半、チームが緊張して硬くなっていると感じていた。リードはされていたが、冷静だった。上田が「BKの組み立てがよくない。早稲田の強いところで勝負している」と指摘し、「ハイパントで敵陣に乗り込め。スクラムを多くしろ」と言ったのを覚えている。FL野澤は、後半15分から慶應が行く、そんなシナリオを思い描き、無駄口は叩かず「気」を蓄積することに集中した。
HOの岡本知樹をはじめFW第一列は、コーチの橋本達矢のもとに集まり、指示を仰いでいた。スクラムを組む時、間合いを詰めろ。そうすればウチの方が重いから押せる。
SH牧野健児の頭の中は真っ白になっていた。早稲田は強い。速いペースはわかっていたのに、対処できない、戸惑い。監督が何を言ったか、全く覚えていない。
上田の指示は明快だった。いつもと同じように椅子の上に立ち、選手たちを見渡しながら、指示を飛ばす。
「ゴール前5メートルのペナルティは全部スクラムにしろ。認定トライでもいい。ラインアウトにはミスがある。それだったら、相手の弱いところで勝負していった方がいい。今のところ、早稲田のミスが少ないせいもあるけど、スクラムが少ないよ、とにかくスクラムだ。スクラム。マイボールのスクラムだったら、ハイパントを上げて、相手のバックスリーにプレッシャーかけていこう。それにタックルが待ちになっている。ディフェンスしに行こう、ディフェンス」
呆然とする選手たちが、この指示をどこまで消化しきれたかは分からない。しかし上田がこだわった「スクラム」が後半になって大きな意味をもつことになる。慶明戦でスクラムトライを奪ったこともあり、早慶戦のスクラムは、慶應が圧倒的に有利と予想されていた。そして慶應FWも、自信を持っていた。しかし前半を終わって、慶應FWは早稲田FWの意外な頑張りに驚きを隠せなかった。HOの岡本は、早稲田スクラムの成長ぶりに舌を巻いていた。
「春のオール早慶戦でスクラムを組んだメンバーと、お互い殆ど同じだったんです。その時は押せた。その感覚があったから大丈夫だろうと思っていたんですが、早稲田はうまくなってました。練習してるなあ、というスクラムでした」
前半はゴール前スクラムでもなかなか押し切れず、スクラムが崩れることもしばしばあった。そんな時、現場ではこんなやり取りも交わされていた。
早「石井さん(当日のレフェリー)ウチは絶対落とすはずはないんだから」
慶「絶対って、その根拠はどこにあるんだ」
思うようなスクラムが組めないことから、慶應FW内にも、ペナルティで迷いが生じていた。前半32分、ゴール前で早稲田がコラプシングの反則を犯す。ゴールラインまであと5メートル、僅かの距離である。試合前のプランなら間違いなくスクラムトライを狙うところだろう。しかし主将の高田はキックでタッチに蹴りだし、ラインアウトから攻めることを選択した。
「あの場面の選択は確かに難しかったんです。岡本が、レフェリーが早稲田側の反則を取り始めたから、スクラムでいけるって言ってきました」
確かにビデオで確認すると、岡本がスクラムを促しているのがはっきり分かる。しかし高田には別の感覚があった。
「スクラムにこだわってトライを取れなかった時のことを考えると、ちょっと嫌でした。それに慶應は別にスクラムにこだわるチームでもないし、だったらラインアウトでの攻め口もあるから、タッチからのラインアウトを選択したんです」
結果的にはこの判断が功を奏し、慶應にとっては前半唯一のトライとなった。しかし上田としては、早稲田が嫌がることを徹底してやっていこう、という気持ちがあったのだろう。
ハーフタイムも終わりに近づき、やっとメンバーに生気が戻りつつあった。しかしそれでもいつもより静かなロッカーの雰囲気を察したLOの巨漢、阿久根潤が叫んだ。
「なに暗くなってんだよ。まだ負けたわけじゃねえんだからよ!」
普段は大人しい阿久根が珍しい強い口調だった。上田はいい兆候だと思った。しかし後半の立ち上がり、早稲田はまたもや情け容赦なく慶應を攻め立てた。
不思議なのは、早稲田も自分たちのペースになっていない、と考えていたことだった。主将の小森の感触は、リードしているチームのものとしては意外なものだった。
「確かにリードはしていました。でも自分たちのテンポで取れたトライではなかったんです。セットから一次攻撃で簡単に取れてしまったり、自分たちが目指していた、相手を振り回して、振り回して取ったトライではなかったんです。そのせいか、慶應は疲れていないな、そう感じていました。それにもっとトライが取れた場面があったんです。いま思えば、あの時点での早稲田は若かった」
この日早稲田FWは予想以上の健闘を見せ、BKによくボールを配給していた。そのこともあり、ハーフタイムでの指示は、早稲田は後半からキックで敵陣に乗り込むことを主眼におくようになる。そして後半最初のプレイで、その思惑は的中した。ハイパントからのタックルが突き刺さり、マイボールスクラムを獲得する、前半と同じ光景がまた40分間続くのか、と思われた。それでも慶應は和田のPGで3点返したが、その直後のプレイで手痛いミスが発生する、早稲田のキックオフからのリスタートで捕球した浦田修平がボールをポトリ。ノックオン、早稲田ボールのスクラムである。早稲田得点の予感が秩父宮に走った。
この時浦田は、牧野、そしてNO8の山本英児と、キックオフの処理について話し合っていたところだった。
「それでキックオフのボールは僕が取っていたんですが、英児と役割をチェンジしよう、と言っていたんです。前半は、僕が蹴り返すと早稲田が蹴り返してきて、英児がそれを取って孤立してターンオーバーが起きていたんです。そんな話し合いをしてたら、もう早稲田が蹴ってきた。ボールが僕に向かってきている間も、まだ話してましたから」
会話が浦田から集中力を奪った。痛恨のノックオン。正直どんな気持ちがしたのだろうか。
「全然、なんとも。僕、もっとでかいミスしてますから」
長崎北出身のウィングは、そこでにっこり笑った。99年1月2日。大学選手権準決勝、明治を追い込みながら、浦田は同じような相手のハイパンの処理でノックオンを犯した。その時は、埋め合わせのチャンスは訪れなかった。今日の早慶戦、彼はこのミスを必死で取り返そうと決心した。そして意外にも、そのチャンスは早くやって来た。次のプレイである。
早稲田スクラム。仕掛けどころの絶好の位置である。しかし慶應が重く早稲田を押し込む。早稲田のフッキングが乱れ、辛うじてボールを抱えたSHの辻高志めがけ、浦田がタックルに行く、ラガーマン言うところの「責任タックル」である。このタックルを起点に慶應は、ボールを奪い返した。
このターンオーバーがゲームの分かれ目になった。いや、早慶両校にとって、シーズンの分岐点になったかもしれないプレイだった。押せなかったスクラムが肝心なところで押せた理由は何だったのか。岡本はハーフタイムの指示通りのことが出来た結果さという。
「コーチの指示通り、スクラムの間合いを詰めてから、早稲田が嫌がりだしたんです。後半の最初のスクラムで、はっきり分かった。相手ボールのスクラムでは、ボールが入れられる瞬間にプッシュをかけるんですが、早稲田はボールを掻くタイミングがめちゃくちゃ速くて、前半はプレッシャーをかけなれなかった。それがあのスクラムで、プッシュするタイミングと掻くタイミングが初めてピッタリ合ったんです」
このスクラムが値千金となったのは、ターンオーバーで奪ったボールを、瓜生のトライに結び付けたからである。しかし、このトライにも、偶然が宿っていた。
浦田のタックルを起点にボールを奪った慶應は、左にラインを敷くが、早稲田のディフェンスラインも人数は揃っていた。司令塔の和田康二の最初のオプションはキックだった。早稲田BKのディフェンスラインの後ろには大きなスペースがあったからだ。おそらくボールを展開すれば、人数が同じなのでタックルラインできっちり止められる可能性が高い。しかし和田はボールを奪ったラックで早稲田が反則を犯し、石井レフェリーが慶應にアドバンテージを取っていることを見逃さなかった。
もし止められても。ペナルティから陣地を稼いでマイボールラインアウトにすることができる。和田は思い切ってFB加藤正臣を飛ばし、瓜生へボールをパスした。
和田が判断を変えるのに要した時間は1秒とかからなかったろう。しかしこの逡巡が慶應には味方した。
パスをもらった瓜生は、和田の逡巡が好結果をもたらした、と語る。
「康二さん(和田)が迷った分、僕の対面の高野さんが康二さんのことを見てしまったんです。それでその隙に外にコースを取って、マークをずらしました」
ビデオで確認すると、一瞬ではあるが高野が和田を見ている間、脚が止まっている。和田の逡巡が「半ズレ」を生む。パスを受けた瓜生は高野の必死のタックルを振りほどき、小森、福田、FB長井真弥の3人を抜いてゴール左側に飛び込む、和田が決して簡単でないゴールを決めて3点差に詰め寄る。このトライでゲームの流れははっきりと慶應に傾いた。
ここからはすべてが慶應に味方した。早稲田のゲームプランさえも、慶應にとってはありがたかった。早稲田は絶妙のラックを組んだお陰で、球出しがスムーズにいった。あまりにボールが出るので驚いたくらいだという。これなら敵陣で勝負した方が有利と判断した早稲田は、キックで敵陣に乗り込むことを戦略に据えた。
コーチの林は、助かった、と思った。早稲田の怒涛の攻撃を予測していたからである。慶應はキック処理も変えていた。浦田が言うとおり、前半は蹴りこまれたボールを蹴り返し、それをウィングがチェイスした。その悪循環を断ち切るため、ウィングが追うのではなく、FWに追いかけさせるようにした。FWを前に出してボールにからませる作戦である。そこから早稲田が蹴ってきたら加藤や浦田が蹴り返して陣地を稼ぐ。早稲田は思ったよりキックを多用してきたので、この作戦は図に当たり、早稲田の思惑とは裏腹に、慶應が地域的に有利に試合を進めることができるようになった。
敵陣にいけば、早稲田FWをがんじがらめにすることができる。そして後半30分過ぎ、上田が左座、中村泰登に代え、濱岡勇介、田中良武の2人をまとめて入れ替える積極的な采配でスクラム戦を圧倒し、32分にはスクラムからNO8山本がゴールラインを陥れ、逆転に成功した。和田の勝負どころでのキックの正確性も勝利に大きく貢献した。
29対21.黒黄、対抗戦優勝。15年ぶりの歓喜である。15年前当時、上田は30代の青年監督だった。コーチの林は大学4年生だった。主将の高田はまだ小学1年生だった。
この勝利は、高田組にとって、大きな意味を持つものとなった。この逆転勝ちによって、それまで自分たちの実力について感じていた自信が「確信」に変わったからである。
FLの三森は、慶應はそれまで全勝では来ていたものの、自分としては、本当の実力についてはまだ疑問を持っていたという。
「明治戦の時は、明治が前の週に帝京に負けて、まだ立て直しが効いていない状態だったし、帝京も大学選手権を狙えるような強さは持っていないと感じました。俺たちは強いはずだ、そうは思っていたんですが、早慶戦の前半で、みんな自分たちの力に疑問を持ったんじゃなかと思うんです。早慶戦に勝って、本当に自信が持てました。多分あれで早稲田が勝ってたら、彼らがどんどん強くなっていったと思います」
大学ラグビーでは、ひとつの勝利、ひとつの敗戦が、チームの行方を大きく左右してしまう。慶應はこの勝利によって、大きく成長を遂げることができた。一方の早稲田は、敗れて自分たちの戦い方をもう一度徹底させようとした。国立競技場で行われた早明戦ではキックを封印し、ワイド攻撃を徹底した。結果は伴わなかった。早明戦以降の早稲田はイデオロギーに殉じたかのように見えた。小森はこの感想に関して、答えてくれた。
「別に失礼ではないです。仰るとおりです。僕らの代は史上最低といわれ、努力して努力してやってきた学年です、だからラグビーの約束事を、きっちり守ることで頑張るしかなかったんです」
早慶戦の勝敗が入れ替わっていたら、大学選手権もまた違った結果が出ていたかもしれない。
キャプテンの高田は、それまで慶應が進んできた道が間違っていなかったことを、早慶戦によって確信する。
「相手によって自分たちの強いところを生かす。単純なことですが、早慶戦でスクラムからのトライを二つ取って、自分たちはこれでいけるんだと自信が持てたんです。ある意味、慶應は『売り』を持たないチームでした。下手をすると中途半端なチームになってしまう危険性もあったんですが、逆に言えばいろんなパターンを持っている。日大戦でスクラムを押されても慌てなかったのは、自分たちの強い部分で勝てると思ったからです」
もし早慶戦で敗れていたならば、戦略面で自信をもつことは出来なかっただろうし、林や高田への不満が出る可能性もあった。11月23日の勝利は、まさに値千金の勝利だったのである。
大学日本一まで、あと4つ、戦いが残っていた。
早慶戦の後、慶應は束の間の休息期間に入った。対抗戦1位を決めた慶應は、12月第3週に行われる大学選手権1回戦まで、ゲームがない。この休養は、増えつつある怪我人の回復に貴重な時間となるし、上田昭夫、林雅人の首脳陣にとっては、戦術の徹底を行うのに絶好の時期といえた。実際、12月9日からは、東京ガスのグラウンドを借りて、ミニ合宿を張っている。
大学選手権1回戦の相手は、リーグ戦5位の法政と決定した。交流試合が行われていた時期を含めて、対抗戦1位のチームがリーグ戦4位、5位のチームに負けたことはない。しかし、この一戦は、気の抜けない戦いになりそうだった。何より法政は、前年のリーグ戦優勝チームであり、LOに身長199センチの巨漢、平塚純司がいることからも分かるように、近年は慶應と同様、選手のリクルーティングに成功し、続々と有望な選手が入学してきていた。リーグ戦の5位という数字は、かえって不気味であり、事実、最終戦では、すでに優勝を決め、法政戦へのモチベーションを欠いていた関東学院を36対16で破り、底力を見せつけていた。安定したスクラム、巨漢LOを活かしたラインアウトを基本に手堅いラグビーを見せるあたり、慶應に似たチームである。一つ一つのプレイの精度が勝敗に直結しそうだった。
12月19日、慶應は26日ぶりの試合を迎えた。第一試合では早稲田と流通経済大が取りつ取られつの激しい戦いを繰り広げ、早稲田が57対41で辛勝していた。サブグラウンドでアップの指揮を執っていた林は、グラウンドから聞こえてくる点数の推移を聞き、気を引き締めてかからなくては、と感じていた。彼としては選手がしばらく試合から遠ざかっているため、ゲームに対する「勘」が鈍っていないかが、心配の種であった。ゲームの序盤に受け身にならないためにも、直前のアップはいつもより激しく行い、ゲームに備えさせた。
ゲーム前、ロッカーから出てきた慶應は、落ち着き払っていた。対抗戦を制した自信が漲っていた。それに比べ、法政は乾坤一擲の勝負を挑むように、気合を入れていた。慶應に涙はなかったが、法政にはあった。
前半戦、慶應は全く精彩を欠いた。久しぶりの試合で、勘が戻っていなかったのか、ゲームのテンポが上がらず、得意のラインアウトも法政の巨漢LOに阻まれ、思ったような展開に持ち込めない。嫌な雰囲気だった。
しかし後半になると、すぐさま逆転、リードしてからの慶應のゲームコントロールは安心できる。もし法政BKに決定力があったら、この試合、どう転んでいたかわからない。33対7.慶應はきわどく法政をかわした。点差ほど楽な試合でなかったのは確かである。
翌週の日大戦も全く同じような展開になった。しかも前半、スクラムを崩されてトライを奪われた。対抗戦最強と言われた帝京にも五分に組んだスクラムが、押された。慶應は新たに勃発した事態に対処しなければならなかった。この時、野澤武史が怪我で欠場したことも大きかった。FLにまわった高田晋作も風邪をひき、FWの展開力は大幅に落ちていた。しかも日大のジャージは新素材でタックルに行ってもツルツルしていて、つかみづらい。これも苦戦の原因になっていた。前半10対19と劣勢のまま終了した。
しかし後半になると慶應は息を吹き返す。BKが走り出し、セットプレイを極力少なくするゲーム展開で、何とか日大を仕留めた。これで二年連続、大学選手権準決勝に進出である。しかし林は肝を冷やしたという。
「負け時というのは、こういう時なんだろうなあ、と本気で思いましたよ」
このゲームの後の林の表情は、シーズンで最も厳しいものだった。
準決勝も前半戦にエンジンがかからない。同志社相手に前半は劣勢。しかし後半開始直後に野澤がトライを挙げると、慶應ペースで有利に展開できた。ノーサイド寸前、同志社の反撃に遭うが、気迫のタックルで同志社の突進をどうにか止め、最後は40メートルほどのPGを栗原徹が蹴りこんで、逃げ切った。
10戦全勝である。しかし部内にはホッとした空気が流れた。キャプテンの高田でさえ、気持ちが緩んだという、
「正直言うと、目標とした準決勝をクリアした時点で、結構みんな満足しちゃったんです。あのままの状態だったら、危なかった」
それまでの慶應の戦いぶりを振り返ると、FWの安定したセットプレイが大きな幹となり、逆転を演出してきた。怪我人の続出で仕上がりが遅れていたBKも、ウィング栗原徹、CTB田中豪人が大学選手権に復帰し、一戦ごとに切れ味を増していった。しかしベストゲームを見たという感覚はなかった。どのくらいのチームなのか、底が見えない、あるいはこのままベストゲームを披露することなくシーズンを終えるのではないか、そんな懸念もないではなかった。
大学選手権、決勝6日前、表参道・スパイラルホールにて、コーチの林に決勝に向けての戦略を聞いた。
「慶應と関東学院は非常に似たチームですね。部内マッチをやるような感じです。ウチもそうですが、オーソドックスなラグビーをするので、びっくりするようなことはして来ません。出来がいい方が勝ちますね」
勝算はあるのか。
「五分五分だと思うんですが、まあ身贔屓で52対48というところですかね。でも戦略で凌駕することは出来ません。選手のプレイの精度で勝敗が決すると思います」
ただし林には自信があったのだと思う。関東学院は大学選手権で最も戦いにくいチームではないと、いつも控えめな彼にしては珍しく明言したからだ。
「法政さんが一番嫌でしたね、今思えば。低いタックルがあるし、我々は法政が関東学院に勝つところを見てましたから、彼らは強いという意識があった。日大戦は、試合中、本当に負けるかと思いました。日大が蹴ったボールが、向こうのラッキーバウンドになったり・・・。負ける時はこんな感じか、と思いました。ディフェンスも悪くて、だから試合後に厳しい表情をしていたんだと思います。準決勝の同志社はですね。今だから言えますが、一番自信がありました。早稲田の試合を分析して、スクラムと近場を抑えれば怖くない、と思ったからです。同志社有利の下馬評もありがたかった」
では関東学院をどの程度の相手と捉えるか。
「いやな方から順番にいくと、法政、日大、関東学院、同志社かな。でも、早慶戦から4試合続けて逆転してますからね、もう負ける気はしないですよ。逆に前半リードしちゃったたらどうしましょうね(笑)」
準決勝から決勝までの13日間。関東学院への分析の時間はたっぷりとあった。もちろんその結果は膨大なものになったが、余分な贅肉を削ぎ、極めてシンプルな形でまとめられた。勝利へのポイントは3つにまで絞り込まれた。
個人的な感想だが、決勝の最初の攻防を見て、慶應が俄然有利と判断した。林から聞いていた分析の結果が、すべて図星だったからである。最初の攻防を振り返ってみよう。
ゲームは関東学院のキックオフで始まった。ボールをキープした慶應が、SO和田康二のキックで敵陣に蹴り返す。ここで最初のポイントが訪れる。林の言葉が脳裏をよぎった。
「関東学院のBKはキックで蹴り返してこないんですね。ランでカウンターに来ます」
予言は的中、慶應BKがタックルに入る。それから4回にわたり関東はラックサイドを執拗についてきたが、慶應のディフェンスが崩れない。1分経過。ここで関東のSO淵上宗志が初めてキックを使い、慶應陣22メートルまで蹴りこむ。慶應FB加藤正臣が再びキック。関東の切り札ウィング四宮洋平がカウンターに出たところをまたタックル、またもラックで関東にボールが出るが、ここで関東は密集で反則を犯し、慶應が先制のPGを決める。
1分30秒もの間、ホイッスルは一度も鳴らず、プレイは途切れなかった。関東のアタック、慶應のディフェンス。慶應はゲインを許さなかった。勝利の鍵のまず一番目のポイントは、「ディフェンスでプレッシャーをかけること」だった。特に関東のSO淵上、CTB吉岡泰一、WTB四宮を徹底的に封じ込める。この最初の攻防で、マークした3人を慶應は見事に仕留めた。とくに「コトが起きるのは淵上の周辺」とマークした司令塔には、生きたボールを展開させなかった。
「淵上君は自陣の深いところでも回してくるので、それをきっちり止めることも大切です」
これも林の予想通りだった。
二番目は「敵陣で戦うこと」。きわめてシンプルな目標だ。しかし林は中盤のゲームメイクに課題を残す慶應としては、自陣から展開しても、意図したような成果があげられないと踏んでいた。それならキックで敵陣に蹴りこみ、好機をうかがおう。単純だがセットプレイに強い慶應には最適の選択だ。
面白いのはこのプランが、防御的発想から浮かんだアイデアだということだ。慶應が敵陣にキックすれば、関東はランからカウンターに仕掛けてくる。それを止めれば陣地が稼げるし、ペナルティを獲得することもできる。よしんばカウンターで抜かれても、慶應には自陣50メートルの「のりしろ」がある。それだけ余裕があれば、いくら駿足揃いの関東BKでも一発でトライを取られることはない。慶應にはその余裕がどうしても必要だった。実際このゲームで最大のゲインを許したのは40メートル。それも関東陣でのことであった。そしてSH牧野健児、和田、田中、加藤が適切な判断で、キックで敵陣に入り、陣地を稼いだことはいうまでもない。
そして勝利への鍵の三つ目は「接点での攻防で負けない」こと。つまりラック。モールなどへの密集戦で決して負けないことである。
慶應は春のオープン戦で関東学院に敗れている。特に前半戦は淵上に翻弄された。彼が後半退くと逆転したものの、最終的には逆転負けを喫した。FWの選手達は、関東の選手はボールへの絡みがうまい、そんなイメージをオープン戦から感じとっていた。しかし決勝の最初の攻防で、慶應は相手ボールを奪うことは出来なかったものの、実際に関東の選手に当たってみると、
「あれっ、こんなもんだっけ・・・」
と意外な感じがしたと言う。
関東の攻め口は分析通りだった。対して慶應はプランを着実に実行し、そして自信を深めていった。慶應の選手達は余裕をもって対応できたのである。決勝で意外な大差がついたのは、偶然ではない(慶應27対7関東学院)。慶應の分析が正確だったことが導火線となり、それを80分間、気迫をもってプランを忠実に実行した選手たちの「精度」が最大の勝因であることは言うまでもない。
しかも最大のポイント、ディフェンス面では全員が素晴らしい働きを見せた。このゲームが今季の慶應のベストゲームになったのは、全員が狂ったようにタックルをこなしたからだ。献身的なFWをはじめ、これまでアタックが目立っていた栗原、田中、瓜生靖治らはこの日、ディフェンス面での働きが目立った。
しつこいディフェンスぶりは、まるで「慶應の遺伝子」が目を覚ましたかのようだった。選手は変われど、伝統校が受け継ぐ遺伝子は簡単には廃れないことには驚きを感じた。
それでも不安が全くなかったわけではない。前半、その殆どを敵陣で戦いながらあと一歩のところでトライが奪えず、得点は4つのPGだけ。しかも前半終了間際には、トライを奪われ、12対7と追い上げられての折り返し。ここ数試合とは展開が逆になっていた。正直、高田にも焦燥感は存在した。
「相手が反則を犯したときも、タッチに蹴ってトライを取って一気にウチのペースに持ち込みたいと思ったんですけど、とにかくリードしていこうという気持ちがあって、ペナルティを狙っていきましたね」
この日の慶應は冒険心にも長けていた。自陣ゴール前でもマイボールスクラム、ラインアウトの局面で、慶應は単純にタッチに蹴りだすのではなく、一旦、FLの野澤武史やNO8の山本英児らのキープ力のある選手が相手に一度突進し、有利な拠点を作ってからタッチを蹴っていた。高田は「キープ力がある選手がいるからできること」と謙遜するが、このひとつのクラッシュが挟まることで、タッチキックを蹴る和田がゆとりをもって陣地を稼ぐことができた。FWの5メートルの突進が、10メートルの差になってかえってきたのである。これも敵陣で戦う、という意思が徹底されたからこそできた戦術である。
そして意外だったのが、精度が高いとされていた関東のプレイの随所に弱点が潜んでおり、そこを慶應が見事に突いたことだった。例えば関東が若干有利とされていたラインアウトだが、実際には192センチのキャッチャー堀田亘頼みで、慶應は十分に絡むことが出来た。もちろん高田が何度もVTRをコマ送りして、相手のタイミングを盗もうとした「予習」の効果もあった。
それでも試合中の関東学院の追い上げは心配の種ではあった。関東は試合中、特にハーフタイム時の修正能力が高いと思われていたからである。しかし彼らは劣勢になった後半も、プランを変えてくることはなかった。淵上のコメントがそれを証明している。
「僕が立つ方に、いつもディフェンスがいた」
淵上の攻撃は、ポイントからいつも順目、順目に来る。これまでのゲームどおり、パターンどおりに守っただけなのだ。怖いのは、それを読み取った淵上が逆サイドに走りこんだりしてくることだった。もちろんその時の対処方法も選手には指示されてあった。しかし関東学院は準決勝までのパターンを踏襲してきた。慶應にとっては関東の攻撃がデジャ・ヴュ(どこかで見たこと)だった。
この日も「後半の慶應」は生きていた。後半開始早々、ウィング浦田修平が右隅に飛び込んでトライ、そして22分には相手ディフェンスのキック処理が薄くなったのを見計らうように和田がインゴールにパントを上げ、楕円球は慶應に味方するように、加藤の胸にすっぽりと収まった。ゴールも成功して24対7.戦意を徐々に喪失していく関東とは違って、慶應の集中力は最後まで切れることはなかった。高田に聞いてみた。いつ頃、勝利を確信したのか、と。
「勝ったと思ったのは、電光掲示板が後半の40分を過ぎてからです。それまで点差なんて関係なかった。ずっと集中が切れなかった」
百周年の歓喜は、意外にあっさりした形で持たされた。慶應はディフェンディング・チャンピオン相手に危なげなく勝利を収めた。新たなる世代の、新しい勝ち方だった。
試合後、ロッカーへ引き上げていく高田と握手した時のことだ。ラグビー選手なのに柔らかく、大きな手だった。彼は目を閉じ、フウッと天を仰いだ。安堵と満足。彼のその時の表情は、一生忘れられそうにない。
優勝から2日後、林、そして高田と共に、再び表参道・スパイラルにて待ち合わせた。
「道を歩いていても、オレたちはやったんだぞ、って胸を張って歩きたくなりますね」
林がそう言って微笑む。
この日のインタビューの最後に、この1年間行ってきた練習を記した日誌を見せてもらうことができた。練習メニュー、そしてその日グラウンドで感じたことが記されている。
決勝まで行った練習204回。毎日毎日、林と高田は練習後に日誌をつけてきた。決勝前日、204回目の主将コメント。
「前に出るディフェンス、キックチェイス、接点。ココでの働きがしっかりできていれば勝機あり。慶應初の単独優勝をして日本一に」
日本一になった翌日に書き込まれた林の感想。
「ラストゲームがベストゲーム・・・204回の練習を頑張った選手に感謝。そしてSHINSAKU,いろいろ大変だったと思うけれど、本当に君は立派。一年間、SHINSAKU、一緒にこのチームで頑張れたことは僕にとって最高に幸せなことでした・・・」
そして主将。
「こんな気分、初めて味わいました、すべてが報われたというか。もう思い残すことはないというか。とにかく心が完全にすっきりしている」
いつも穏やかなキャプテンだが、いつにも増して穏やかな表情をしている。
「その時の気持ちがずうっと続いている感じなんですよ・・・」
取材の途中から上田が加わった。周りでコーヒーカップを口元に運んでいた人の手の動きが止まった。
上田を前にすると、いつもこの人物の強い星の巡り合わせを感じてしまう。15年前は青年監督として悲運のスローフォワードを経験し、翌年には自ら所属する会社を破って日本一。どん底のチームを引き上げ、6年目で大学王座奪回。しかも創部百周年の記念すべきシーズンに。今回の優勝は上田なくしては決して成し遂げられなかったものである。
果たして彼の人生は「強運」という言葉で片づけてしまっていいのだろうか。そんな疑問を本人にぶつけてみる。
「いや、運を呼び込むにはね、努力しないことには何も始まらないと思うんだ。去年の1月2日、明治に逆転負けした悔しさがあるから、今、このチームがある。そして我々は努力した。その日ごろの努力に女神が微笑んでくれた、そういうことだと思うんだ」。
以上、『慶應ラグビー 百年の歓喜』(生島淳 著 文芸春秋刊)より引用させていただいた。文字通り、「慶應ラグビー 百年の歓喜」である。
以 上