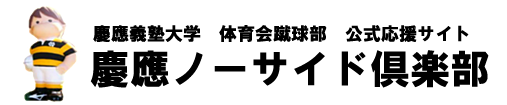世田谷の塾員
2020年が如何に異常な年であったかは、誰もが理解している。
例年、大学ラグビーは、チーム組成の過程で春季大会があり、B、Cの試合が並走し、夏合宿があり、秋の対抗戦本戦が幕を開ける。そしてシーズン中も、ジュニア選手権があり、C以下も試合が続く。それが常識的なスケジュールだった。
コロナ禍は、すべての人々から、日常と常識を奪ってしまった。
コンタクトの激しいラグビーにあっては、コロナの影響は深刻だ。
天理、日体、東海、そして同志社。彼らの苦悩は察して余りある。
塾蹴球部はコロナ対策のため、本当に徹底した管理体制を敷いた。試合に出る、出ないにかかわらず、部員は公共交通機関の利用を避けて、練習に参加した。そのために片道数時間をかけて自転車で自宅と日吉とを往復する。部員間の接触を制御する。そして練習メニューも制約を受けた。
地を這うような際限のない努力を、4年生が先頭に立って徹底していった。
彼らの全てが試合に出られるわけではない。いや、今年はB以下の試合が制約されるため、本当にラグビーの試合への出場機会は限られている。それなのに、そんな中で、彼らは黙々と自らの為すべきことを遂行していった。
ONE TEAMという言葉は、試合に出られない部員も含めた言葉だ。本当の意味でのONE TEAMが試される中で、塾蹴球部は、匍匐前進を続けていった。
そして秋。初戦の筑波戦は、文字通り、今シーズンの初めての試合であった。皆の逸る気持ちが抑えられなかったのだろう。チームとしてのゲーム運びも手探りであった。後から振り返って、塾は勿体ない星を落とした、と感ずる。しかし、それもまたラグビーだ。
今季の最初の白眉は、慶明戦だろう。ディフェンシブに闘う、というチーム・コンセプトが、一人一人に徹底された。15人が一つになって、徹底してディフェンス・ラインを押し上げ、適切なスペーシングを追求した。あまり良い席で観戦できなかった小生は、明治が凡庸なアタックをしていた訳ではないことを明瞭に理解できた。ボールを素早く小刻みにパスして、ディフェンス・ラインの穴を探す。とても明治とは思えないような機敏なアタックを重層的に試みる。しかし塾は、徹底してボールキャリアを自由にさせなかった。三木に代表される戦略的ディフェンスは、ボールが動く先を常にノミネートして当たっていた。
明治の最初のトライは、アドバンテージ・オーバーのタイミングが演出した偶然の産物だ。二つ目のトライは、塾の唯一といってよいミスタックルを、明治が衝いた格好だ。
しかし塾は慌てなかった。そして攻撃的ディフェンスがもたらす数少ないチャンスを確実に得点に結びつけていった。最後のPGがポストの間を通過するのを見て、涙は流れなかった。戦略的成功が形になった必然の勝利だからだ。小さくガッツポーズを結んだ。
早慶戦は、悔しい敗戦となった。慶明戦の衝撃が大きかったのだろう。早稲田はその試合をベースに、よくスカウティングしてきた。ボールを持つと、FWがタテ、タテと突っ込み、塾のディフェンスを集めてから、浅い角度でボールを広く動かして、BKがタックルしにくい形でゴールラインを割ってきた。「シティを作って、カントリーで攻める」という原則を、塾のディフェンスに当て嵌めて、薄みを作り出してきた。
早慶戦における塾の課題は、得点力だったと思う。相手ゴール前まで行って取り切れない局面が再三見られたが、アタックのオプションが限られることは、攻める者としては難しく、守る側としては的を絞り易くしたといえる。
この課題を克服していったのが帝京戦だった。塾蹴球部は、慶明戦に続き、最後のワンプレーで劇的逆転勝利を飾った。1シーズンに二度、こうした劇的勝利を演じるのは、記憶に基づけば、1984年度以来のことである。
帝京戦勝利の価値は計り知れない。何よりFWのアタックに、自信の持てる選択肢を増やす実績を作った。帝京相手にラックサイドを3度も割ってスコア出来たのは、自分達には限りない自信を与え、今後対戦する相手チームには底知れない脅威となる。ボールキャリアがコプレイヤーとバインドし合ってゴールラインを割っていくプレーは、それが来ると分かっていても止められない。何故なら、あの帝京が止められなかったのだから。そしてこのオプションは、攻撃的ディフェンスでノットが取れれば、突然そのチャンスがやってくる。帝京が、ロスタイムのキックオフ・リスタートから反則二つで自陣ゴール前まで到達されてしまったように。
そして、たとえそれがFW偏重であったとしても、こうした攻撃パターンを確立した塾のゲームプランは、早慶戦の時とは比べるべくもなく、進化しているといえる。
今年の相部組は、シーズンが深まるにつれ、飛躍的な進歩を遂げている。こうした進歩は、ひとえに、例年にない厳しい環境を、4年生が自らを律して乗り切ろうとしている自助努力が形になって現れているものだと思う。小手先に囚われない強い意志と信念が、結果として試合に現れて、彼らは努力に相応しい勝利を手にしているのだ。
帝京戦は、実に80分が経過した時点で、20対27と負けていた。誰がこの試合の結末を予測しえただろう。負けを覚悟していた小生は、ノーサイドの笛とともに、勝利の感激に堪え切れず号泣した。塾蹴球部を応援する者として、久々に嬉しい涙だった。